
また、多くの企業のカスタマーサポートセンターでは、オペレーター不足により応対ノウハウなどのナレッジが属人化しやすいという課題に頭を悩ませています。
こうした課題を解消するために、ここ数年で多くの企業で導入が加速しているのが「チャットボット」です。
本記事では、EC業務において、チャットボット導入がもたらす具体的な効果について解説しています。
「EC向けチャットボットの導入メリットは何か?」「実際にどの業務が自動化できるのか?」という方はもちろん、「チャットボットと有人対応のハイブリッド運用方法を知りたい」「ユーザーの離脱を防ぐチャットシナリオの設計方法について調べている」という方も、ぜひご一読ください。
なぜ今、ECにチャットボットが必要とされているのか

顧客との接点やニーズが多様化・複雑化
昨今、デジタル化が進み、消費者の行動パターンが多様化・複雑化したことが、チャットボットの導入が進んだ背景の一つになっています。
以前であれば顧客からの問い合わせ経路は電話かメール、あるいは問い合わせフォームなどに限られていましたが、現在はSNSの普及により各種メッセージなどがそこに加わっています。ECサイト事業者は、このように複雑化・多様化した顧客との接点やニーズに対応することが求められています。
また、インターネットの普及により、時間や場所に限定されない対応が顧客から求められ、企業は24時間365日対応できる体制の構築が急務となっています。
チャットボットの導入により、こうした課題をクリアするとともに、品質にバラツキのない顧客対応が可能となります。
ユーザー離脱の軽減とCVR向上が期待できる
ECサイトを訪れた顧客が、商品を購入せずに離脱する要因はいくつかありますが、チャットボットによって購入までの不明点が解消できれば、離脱を軽減することが可能です。
たとえばチャットボットが決済サービスのサポート対応をすることで、商品をカートまで入れたにもかかわらず、購入に至らなかったユーザーをフォローすることができ、売上に直結すると言えます。
また、チャットボットと「商品管理システム」「在庫管理システム」「出荷管理システム」などと連携させれば、顧客からの「商品の色やサイズ」や「再入荷の予定」、「配送日や配送料」などに関する質問があった場合でも、速やかに答えることが可能に。
これにより、ECサイトでの購入に慣れていないユーザーに対し、注文までサポートすることで、CVR向上が期待できます。
顧客からのフィードバックを分析できる
リアル店舗と違いECサイトの場合は、商品やサイトに対する意見・感想など、ユーザーからの声を直接得られる機会が少なく、改善点を見つけることが難しいというデメリットがあります。
顧客にレビュー投稿やアンケートへの協力を依頼することもできますが、積極的に回答する顧客はもともと満足度が高いため、良いコメントばかりが集まってしまう傾向にあります。
商品詳細ページやカテゴリーページ、FAQページなどに設置したチャットボットに自由入力欄を実装すれば、顧客が求める商品の傾向や、よくある疑問などの情報を得ることができ、商品やECサイト改善につながります。
ECサイトで活躍するチャットボットの具体的な機能
チャットボット(chatbot)とは、リアルタイムでメッセージをやり取りする「チャット(chat)」と、ロボットを意味する「ボット(bot)」を組み合わせた造語です。ECサイトに訪れたユーザーからの質問に、自動で返答するプログラムを指します。
世の中には、Q&Aを得意とする業務効率化に特化したFAQチャットボットや、AIチャットボットなど、 多くのチャットボットが存在します。ここでは、ECサイトで活躍するチャットボットの具体的な機能をご紹介します。
よくある質問への対応
チャットボットを導入することで、下記のような定型的な問い合わせへの自動回答が可能になります。
・決済サービスのサポート対応
・商品や在庫に関する問い合わせ対応
・色やサイズに関する問い合わせ対応
・配送日や送料に対する問い合わせ対応
これにより窓口の人的リソースを削減すると同時に、より複雑な問題や高度な判断が必要な業務へとシフトできるでしょう。
また顧客から寄せられた質問に対して、チャットボットが24時間365日即座に回答することで、顧客の待ち時間を大幅に削減することもでき、質の高いサービスを提供できる環境が整えられます。
入力補完機能とレコメンド機能
たとえチャットボットが実装されていたとしても、初めて訪れるECサイトでは、顧客は何を入力すればいいかわかりません。
入力補完機能は、何かしら文字を入力すれば候補となるFAQや問い合わせ内容が複数表示されるため、入力の補助だけでなく顧客のリテラシー不足を補うことができます。
また、チャットボット上で、閲覧回数の多いFAQや問い合わせ内容を最初に提示することで、顧客との会話を進めていくのがレコメンド機能になります。
より閲覧の多いFAQや問い合わせ内容を提示するため、多くの顧客が回答を求めている疑問や知りたいことである可能性が高くなり、顧客満足度も得られます。
さらに、パーソナライズ機能を持っているチャットボットでは、より顧客にマッチしたレコメンドが提示でき、高い確度でコンバージョンを得られるようになります。
会話ログやアクションデータの収集と分析
チャットボットの分析機能を使えば、会話ログやユーザーのアクションデータを収集・分析することができ、よりチャットボットの精度を高め、顧客の利用満足度を上げていくことができます。
有人対応への切り替え機能
ユーザーが求める回答が相談ベースのものだったり、チャットボットでは回答できない複雑なものだったりした場合に、オペレーターなどの有人対応に切り替えることができる機能があります。オプションで追加できることが多いです。
ECサイトでのチャットボット活用事例
次に、チャットボットの導入に成功した企業の事例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
花キューピット〜ローンチ後に改善を繰り返し未回答率を1割に〜
花キューピット株式会社では、フラワーギフトの受注サービスにおいてカスタマーセンターを設置していますが、オペレーターのみでは最繁忙期のお問い合わせに対応できないという課題を抱えていました。
そこで、顧客が問題や悩みを自己解決できるようチャットボットを導入。すでに存在するQ&Aデータを使用することで、2週間弱でのリリースに成功しました。
調査の結果、チャットボットのローンチ直後は「答えられなかった質問」が約2割あることが判明したため、それら一つひとつを地道に改善。最終的に未回答率を約1割までに抑えることに成功し、顧客満足度の向上を図っています。
ファンケル〜チャットボットと有人チャット、FAQシステムを連携〜
株式会社ファンケルでは、化粧品やサプリメントなどの定期便サービスを利用する顧客が多く、それまで変更や停止などの手続きの案内については、電話とWebのマイページで行っていました。しかし顧客からの「マイページのID・パスワードを忘れてしまいログインできない」といった問い合わせが多く、その際は電話での案内に追われていました。
そこで、カスタマーサポート専用のLINEアカウントを開設する事により、問い合わせ導線を改善。さらに、チャットボットと、有人チャットシステム、FAQシステムを連携することで「LINE公式アカウント上での本人特定」および「お問い合わせの自動化」を実現することに成功。
現在では、LINEやWebチャットでも、個々の顧客の要望に応じて手続きを行えるようにしています。
ユニクロ〜着こなし投稿アプリと連携し回答の幅を拡大〜
ユニクロでは、ECサイトでの購入をサポートするAIチャットボットサービス「IQ」を導入。過去の問い合わせ内容や情報をもとにAIがお客様からのお問い合わせに対応し、AIで回答できない質問や悩みには、オペレーターがリアルタイムチャットで回答するなど、AIと人の利点をうまく組み合わせた接客を行っています。
「IQ」は、オンラインストアのログインページ、ジェンダー別のトップページ、決済ページに設置され、「ログインできない」「決済や受け取り方法について教えてほしい」といった問合せの対応だけでなく、「着こなしを提案してほしい」といった要望にも迅速に答えることができます。
さらに、同社の着こなし投稿アプリに投稿された画像も検索できるなど、顧客の悩みや質問に対する回答の幅をさらに広げています。
アスクル〜チャットボットがオペレーター6.5人分の業務量に対応〜
アスクルは、シナリオ型チャットボットの導入により、顧客サポートの品質を大幅に改善することに成功しています。
以前はメールによる問い合わせがメインで、顧客とのやり取りには平均で2.5往復を要し、さらに注文数の増加により負荷が急増するという課題を抱えていました。そこで、利用者による自己解決促進を目的にチャットボットを導入した結果、問い合わせの約5割はチャットボットで対応可能に。回答率も97%と高く、最大でオペレーター6.5人分の業務量である、月1万件以上の問い合わせ対応を実現しています。
チャットボットの導入により、カスタマーサポートセンターの運用負荷軽減に成功した好事例と言えるでしょう。
小林製薬〜チャットボットの導入により顧客満足度が97%に〜
小林製薬では、消費者の自己解決ニーズに応えようとFAQサービスを導入していましたが、解決率の低迷といった課題を抱えていました。そこで、製品問い合わせページの「お客様相談室」にシナリオ型のチャットボットを導入、顧客からの問い合わせに常時対応できる体制を構築しました。
これにより利用者の自己解決率が格段に高まり、「お客様相談室」の満足度は97%までに達しています。
今後は、チャットボットの適用範囲を拡大することで有人対応の負荷を抑制しつつ、さらなる顧客満足度の向上に努めています。
チャットボット導入で失敗しないためのポイント
それではここで、チャットボットを導入するにあたって、気をつけるポイントなどについて解説をしましょう。
チャットボット化の業務範囲と目的を明確にする
チャットボットを導入する前に、まず大事なのが、現在の業務の棚卸しをし、チャットボットに置き換える業務範囲を明確にすることです。
顧客導線やタッチポイントの洗い出しをし、それぞれで発生するカスタマーサポート業務について、作業内容、頻度、所要時間、人の判断の有無など具体的に書き出します。
さらに「工数が多い」「ヒューマンエラーが発生しやすい」など、作業における負担や課題点などを重ねることで、チャットボットを導入する業務範囲と目的を明確にすることができます。
シナリオ型は初期設計が重要
チャットボットには、想定される質問に対してあらかじめ回答を用意しておき、顧客からの問い合わせに応じて選択肢を提示し答えまで導きだす「シナリオ型」と、過去の記録やデータを参考にして自動で回答を導き出す「AI型」があります。
たとえば、配送状況や返品手続きなど、定型的な質問が多い場合はシナリオ型が適しています。シナリオ型は導入コストが低く運用も比較的容易ですが、その一方でシナリオ構築に失敗すると破綻してしまうので、初期設計には十分に時間をかけましょう。
自社の状況に応じて最適なタイプを選ぶ
チャットボットには、大きく分けて「ASP」「オープンソース」「スクラッチ」の3つのタイプがあります。
それぞれメリット・デメリットがあるので、自社に最適なタイプを選びましょう。
①ASPタイプ
クラウド環境を利用するタイプのチャットボットで、比較的費用負担が少ないタイプと言えるでしょう。
ただし費用だけで選ぶと、期待したパフォーマンスを得られない場合もあるので、導入する際や運用中のサポート体制も含めてトータルで検討することが重要です。
②オープンソースタイプ
自社にエンジニアがいる場合、オープンソースを利用すれば開発期間やコストを大幅に圧縮することができます。
ただし「カスタマイズをしてしまうとバージョンアップができない場合がある」「サイバー攻撃を受けるリスクがある」などのデメリットもあるので、注意が必要です。
③スクラッチタイプ
自社に最適なチャットボットを一から作る方式です。「在庫システムや顧客システムと柔軟に連携可能」「自社のセキュリティ基準に適応できる」など、完全に自社用の仕様に作り上げることができます。
ただし相応の開発費用と期間が必要となるので、慎重に検討しましょう。
まとめ
ここでは、チャットボットが必要とされている背景から、具体的な機能、活用事例、導入の際の注意ポイントなどについて解説してきました。
チャットボットは、業務効率化だけでなく、売上や顧客満足度向上にも直結する施策です。
しかしチャットボットを導入する際には、自社のカスタマーサポート業務やECサイトの利用状況などを的確に分析し、適切なシステムを選択することが重要です。
ルビー・グループではこれまで、数多くのラグジュアリーブランドにおけるECの構築、マーケティング、 オペレーションなどを手がけ、様々なマーケティングソリューションをご提供しています。
チャットボットの導入を含め、カスタマーサポートの品質向上や売上の拡大などに関するご相談などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

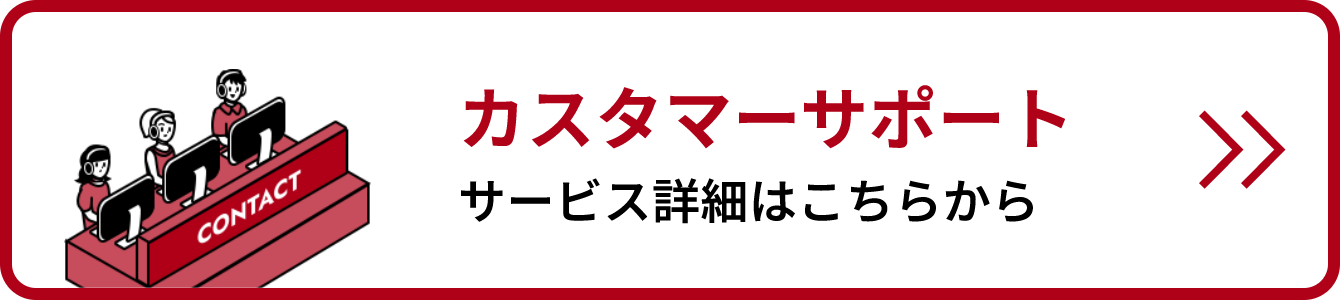
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





