
本記事では、2003年から2004年にかけてインバウンド需要が増えた背景や、2005年に
入ってから急減速している理由、国内ラグジュアリーブランドが直面する課題、インバウンド後の世界を見据えたブランド戦略などについて紹介しています。
「最近インバウンドが減ったのはなぜ?」「インバウンド売上が下がった今、ラグジュアリーブランドはどうすべきか?」といった疑問や悩みをお持ちの方はもちろん、「国内マーケットのLTV向上に有効なCRM施策とは?」「REDやWeChatなどのSNSを利用した訪日外国人との接点づくりはどこまで必要?」とお考えの方も、是非ご一読ください。
ビザ緩和と円安で膨らんだインバウンド需要―背景と2024年までの盛り上がりを振り返る

2003年には訪日外国人旅行者数が約2,500万人、消費額は5.3兆円と、それまでの記録を更新。さらに2024年には、同3,686万9900人、同8兆1,257億円(一人あたりの旅行支出 22.7 万円)となり、前年比で53.4%増、2019年比では69.1%増となっています。
円安とともに、インバウンド需要拡大の要因として考えられるのが、以下のポイントになります。
>>ペントアップ需要(繰越需要)
コロナ禍で渡航を控えていた需要が、2023年以降に顕在化
>>観光庁の政策効果
訪日外国人旅行者数の増加と消費額の拡大を目指し、様々な施策を講じている
>>LCCの就航
訪日旅行の選択肢が拡大これらに加え、中国政府による「団体旅行の解禁」「ビザの緩和」などの施策により、中国からの旅行者数もコロナ禍以前の訪日客数の水準へと回復が継続しています。
2024年の訪日外国人旅行消費額は、国籍・地域別でみると、中国が1兆7,265億円(構成比21.2%)、台湾が1兆936億円(13.4%)、韓国が9,632億円(11.8%)、米国が9,021億円(11.1%)、香港が6,584億円(8.1%)の順となり、この上位5カ国・地域で全体の65.7%を占める結果に。2023年と比較すると、中国が7,604億円から大きく増加し、台湾も7,835億円から1兆円を超える消費額となっています。
また、訪日外国人旅行消費額を費目別にみると、宿泊費が33.6%と最も多く、次いで買
物代(29.5%)、飲食費(21.5%)の順になっており、2023年に比べ、買物代の構成比が増加しています。
さらに訪日外国人の旅行消費額を1人当たりでみると、宿泊費は英国が17万円、オーストラリアが16万3,000円、娯楽等サービス費はオーストラリア(3万円)が、買物代は中国(11万9,000円)が最も高いという結果になりました。
これらにともない百貨店のインバウンド売上高は、2024年に6,487億円となり、前年比85.9%増と大幅に増加して過去最高を更新。特にラグジュアリーブランドを中心に、高額商品の購入が増加しました。
※データ参照:観光庁【インバウンド消費動向調査】2024年暦年の調査結果(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856155.pdf)
2025年4月以降に見えた“バブルの終焉”―訪日客の消費動向が変わった理由とは?
2023年、2024年と日本経済を押し上げてきたインバウンド需要ですが、2025年に入りブレーキがかかっています。
ここでは、その現象を細かく見るとともに、要因について解説していきます。
観光庁のインバウンド消費動向調査(※1)によると、1〜3月期の外国人旅行者1人当たりの支出額は前年同期比5.2%増の22.2万円と、全体のインバウンド消費は衰えてはいません。しかし、中国人の支出額は13.7%減の25.6万円と大幅に下落。
また百貨店の免税売上も減少しており、日本百貨店協会の発表(※2)によると、5月の免税売上高が前年同月比41%減で、3カ月連続の前年割れとなっています。なかでも高級ブランドなど高額品の売り上げが低調で、1人当たりの購買単価も37.4%減の約7万9,000円と、大きく減少しています。
円高が進んだことや、原材料費の高騰などで高級ブランドの値上げが相次いだことを受け、日本で購入する「お得感」が薄れたことが影響したとみられる一方で、インバウンドも多様化し、買い物の価値観が変わってきていることも要因の一つとして挙げられています。
なかでも中国からの観光客は、「量」だけでなく「質」の面でも、これまでとは異なる傾向が見られるようになりました。
これまで主流だった都市部での買い物中心の旅行から、地方志向の観光スタイルへとシフト。訪日回数の増加とともに、東京・大阪といった主要都市の訪問率は低下し、地方エリアの訪問率が上昇傾向にあります。
とくに北海道は、広大な自然や温泉、グルメなどが楽しめるため、中国の富裕層を中心に人気があります。ニセコやルスツなどのスキーリゾートは、冬のウィンタースポーツを楽しむために多くの中国人観光客が訪れています。
また、温泉やグルメ、歴史的な観光スポットなどが豊富な九州は、幅広い層の中国人観光客に人気があります。特に、別府や由布院などの温泉地は、リラックスや癒しを求める観光客が数多く足を運んでいます。
その他にも、沖縄は美しい海やビーチ、亜熱帯の自然が人気です。さらに、「自然体験ツアーの参加」「映画・アニメの聖地巡礼」のような体験型イベントを重視する中国人観光客が増えているのも特徴。
写真や動画映えするためSNSで共有するのに最適で、SNSを活用するZ世代を中心に、こうした体験型イベントニーズは今後も拡大していくことが予想されます。
中国人観光客の消費の内訳をみても「買い物代」が減少する一方で、「宿泊費」「飲食費」「娯楽・サービス費」が増加していることから、「爆買い」から「体験・満足度重視」の旅行スタイルへのシフトは、今後も加速していくでしょう。
(※1)データ参照:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html
(※2)データ参照:https://www.depart.or.jp/press_release/files/NL2505.pdf
ラグジュアリーブランドが直面する3つの課題―インバウンド偏重からの脱却が必要に
それでは、インバウンド需要が分散化・多様化した今、ラグジュアリーブランドをはじめとする、国内の物販事業者が抱える3つの問題点について見ていきましょう。
インバウンド依存の集客構造の限界
大手百貨店4社の2025年5月度売上を見ると、三越伊勢丹の免税売上は、前年同月比33.0%減。基幹3店(新宿、日本橋、銀座)合計でも同30.2%のマイナスとなっています。
大丸松坂屋百貨店も、免税売上高が前年同月比40.1%減と大幅な落ち込みを見せました。訪日客数自体は同2.9%増だったものの、ラグジュアリーブランド、時計、宝飾品など高額商材の販売が低迷し、客単価は同41.7%減と大きく落ちています。
髙島屋も、免税売上は同41.7%減とマイナス幅が大きく、ラグジュアリーを中心とする高額品の不調が全体に影響しています。
阪急阪急百貨店は全店、旗艦店の阪急うめだ本店ともに、免税売上高が約4割減。モードやインターナショナルブランド、バッグ類が特に影響を受けています。
ラグジュアリー商品を中心とした訪日客の高額品消費の勢いの弱まりは明らかで、インバウンドに依存した集客構造は限界に来ていると言えるでしょう。
インバウンドCRMの未整備
インバウンドCRMとは、訪日外国人観光客の情報を一元管理し、マーケティングやサービス向上に活用するシステムのことです。国内ラグジュアリーブランドは、このインバウンドCRMが構築・整備できているとは言えず、そのため以下のような問題に直面しています。
【顧客情報の把握不足】
訪日外国人観光客のうち、誰がいつ、どこから来て、何に関心があるのか、といった情報が把握できず、パーソナライズされた情報提供や効果的なプロモーションが困難に。
【顧客体験の低下】
訪日外国人観光客のニーズに合った情報提供やスムーズなサービス提供ができなくなり、顧客満足度が低下。
【リピーター育成が困難】
顧客との継続的な関係構築が難しく、訪日外国人観光客のリピーターを増やすことが難しくなります。
このような課題を解決しないままでいると、いつまでたっても顧客のニーズに合った商品やサービスを提供できず、売上機会を逃す可能性が拡大するばかりです。
越境EC未整備による機会損失
日本国内で自社取扱商品を購入した訪日観光客に、帰国後もリピート購入してもらうためには越境ECの存在が重要になります。
経済産業省の「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」(※)にある、BENNOSグループが実施した「越境 EC の利用意向調査(2021 年 9月実施)」によれば、「訪日した後、越境 EC で気に入った商品をリピート購入したいか」との質問に対し、「思う」が54.7%、「やや思う」が29・7%で、8割以上が「訪日後にリピート購入をするにあたって越境 EC を利用したい」と回答しています。
越境ECが構築されていない、あるいは未整備の状態だと、「日本で購入した商品を自国から再購入したい」「日本で見たものを自国に戻ってから購入したい」というニーズに応えることができず、大きな機会損失になってしまいます。
(※)データ参照:https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf
インバウンド後の世界を見据えたブランド戦略とは―ECと実店舗の再定義へ
インバウンド需要の様相が大きく変化した今、ラグジュアリーブランドはどのような方向転換や戦略立案が必要なのか。ここでは3つの観点で解説していきます。
現地SNSと越境ECとの連動によるリピート購入の仕組み化
多くの富裕層を抱える中国人で商機を勝ち取るためには、「小紅書(RED)」「WeChat(微信)」といった現地SNSと、越境ECサイトとの連動が欠かせません。
「小紅書(RED)」は、30歳未満の女性を中心に3億人が利用していると言われるソーシャルプラットフォーム。主にライフスタイルや美容、コスメ、ファッション、旅行、グルメなどの情報を共有する場として知られています。
「小紅書(RED)」はコミュニティ性が高く、ユーザー同士の交流が活発なのが大きな特徴で、投稿に対するエンゲージメント(いいね・コメント・シェア)が非常に高く、口コミ効果が期待できます。
さらに、商品のタグ付け機能が充実しているため、特定の商品のレビューや情報を見つけやすくなっているのが特徴。ユーザーが商品に関する情報を効率的に収集しやすい、多くの中国人にとっての消費意思決定プラットフォームとしてのポジションを築いています。
「小紅書(RED)」をマーケティングに活用すれば、効果的に中国国内で自社商品を紹介し、越境ECでの売上増加に繋げることができます。
「WeChat(微信)」は、中国版LINEとも言われるメッセンジャー機能を中心としたマルチサービスアプリで、インバウンド客の多い日本企業のマーケティングにおいて有効なツールです。
たとえば、来店時に利用できるクーポンページを公式アカウント内に設置することで「旅中」での来店を促進。さらに、実店舗にWeChatの公式アカウントやミニプログラムのQRコードを掲載し、来店・購入していただいた顧客に対して公式アカウントへのフォローを誘導します。
また、公式アカウントをフォローしたユーザーに対して、記事配信、DM、WeChatグループでの日々のコミュニケーションを行うことによって、顧客のファン化やリピーターの獲得、友人への紹介、越境ECでの購入などに繋げていくことができます。
国内シン富裕層の開拓と囲い込み
インバウンドに代わる軸として、改めて注目されているのが、国内の新富裕層になります。
新富裕層とは、ベンチャー企業経営者や投資家、YouTuberやインフルエンサーなど、一代で財を成した20〜40代前半を中心に構成される層を指します。
頑張った自分へのご褒美として、高価格帯の商品やサービスを積極的に購入する「ご褒美消費」の傾向が強い点が特徴です。
大手百貨店では、こうした国内の富裕層を対象に単価の高い外商サービスを強化しており、サービス内容や接客環境の充実、外商組織の改編に取り組んでいます。特に都心部店舗では20~30代の若い外商客が増えていることを受け、同年代の外商員を増員。多層化する外商客の個々のニーズに合わせた対応を行っています。
また、現役世代のベンチャー経営者などは多忙で、タイパ重視派が多いことから、モバイルツールを駆使した「デジタル外商」を積極的に展開。オンラインでの情報収集や購買を好む傾向が強いデジタルネイティブ層のために、WEBメディアの拡充や、SNSでの情報発信強化を積極的に進めています。
オンライン接客やチャットコマースの強化による接点の維持
人的リソースに依存しない、品質の高い顧客との接点づくりも、今後は重要になっていきます。
そこで重要になるのが、ECサイトへの「チャットボット」や「AI接客」の導入です。チャットボット(chatbot)とは、ECサイトに訪れたユーザーからの質問に、自動で返答するプログラムを指します。利用者からのよくある質問への対応や、入力補完や商品レコメンドなどを自動化できるため、購入までの不明点が解消して利用者の離脱を軽減することが可能になります。
たとえばチャットボットが決済サービスのサポート対応をすれば、商品をカートに入れたままで購入に至っていないユーザーをフォローし、売上ロスを防ぐことも可能になります。
また、チャットボットと「商品管理システム」「在庫管理システム」「出荷管理システム」などと連携させれば、顧客からの「商品の色やサイズ」や「再入荷の予定」、「配送日や配送料」などに関する質問に対し、自動で速やかに答えることが可能になり、CVR向上が期待できます。
AI接客とは、AI技術を利用して顧客とのコミュニケーションを行うサービス手法です。AIによる自然言語処理や機械学習アルゴリズムを搭載し、質問や問題に対して人のような理解と適切な対応を提供します。
消費者からの複雑な質問やクレームにも適応し、高度な問題解決能力を発揮。また、複数の言語に対応し、国際的な顧客層にも柔軟かつ効果的なサービスを提供できます。
従来の人間による接客業務の一部をAIで代替することにより、24時間365日接客が可能になるばかりでなく、「人手不足や人件費高騰」「顧客ニーズの多様化」にも対応。また、「サービス品質の均一化」により「顧客満足度向上」を図ることも可能になります。
まとめ
インバウンド集客に依存した“爆買いモデル”は限界を迎え、ECと店舗、双方で“購買以外の価値”を提供できるかどうかが、ブランドの生き残りを左右する時代に突入したと言えます。
そこでキーワードとなるのが「CRM」「越境EC」「オンライン接客」です。顧客の属性や行動特性を把握し、購買意欲を高める販売戦略を打ち出すことができる「CRM」は、顧客満足度の向上やリピーター育成には欠かせません。
「越境EC」は、現地で店舗を構えるよりもリスクを抑えつつ、低コストでビジネスを展開することができるのも大きなメリットです。
また、「オンライン接客」は、単なる効率化だけではなく、「接客品質の平準化」や「売上最大化」に貢献し、新富裕層の拡大や、今後の店舗・EC運営において競争力の鍵になります。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

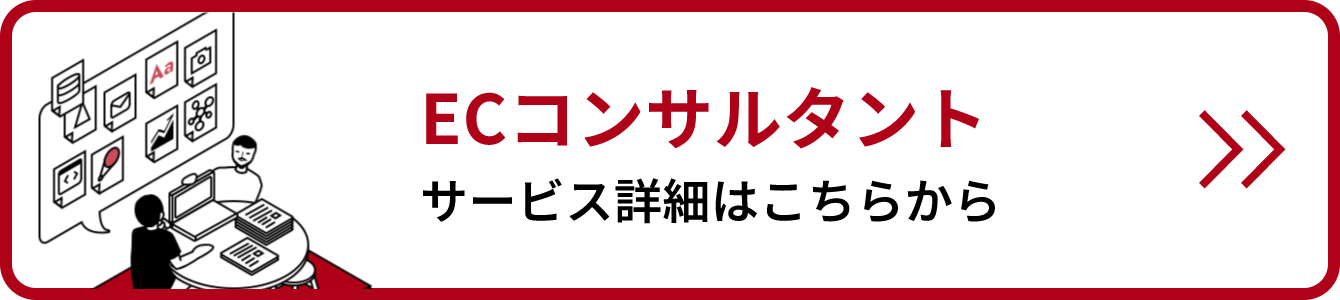
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





