
それだけに「ECサイトのカテゴリーページや商品一覧ページでページネーション設計に悩んでいる」「無限スクロールや「もっと見る」ボタンと比較して、どれが最適か判断できない」といった悩みはつきないものです。
本記事では、ECサイトのページネーションの基本と重要性について詳しく解説しています。
「ページネーションの基本定義や役割を知りたい」「SEOに適したページネーションの設計方法が知りたい」という方はもちろん、「自社ECサイトに最適なUIとは?」「ページネーション変更によるSEO順位変動リスクの有無についても知っておきたい」という方も、是非ご一読ください。
ページネーションとは?ECサイトにおける役割と重要性

ページネーションは、膨大な数の商品やコンテンツを、一定数ごとに区切って複数のページに分割し、ユーザーが「次のページへ」「前のページへ」といった操作で各ページを移動できるようにする仕組みです。これにより、以下のようなメリットが生まれます。
表示速度の向上
多数の商品を一度に表示しようとすると、ページの読み込みに時間がかかります。ページネーションにより、表示する商品の数を制限することで、ページの表示速度が速くなり、ユーザーのストレスを軽減します。
ユーザビリティの向上
ユーザーは一度に大量の情報に圧倒されることなく、区切られた情報群を順に確認できます。また、どのページを見ているのか、全体で何ページあるのかを把握しやすくなります。
サーバーへの負荷軽減
一度にすべてのデータを取得・表示する必要がないため、サーバーへの負荷が軽減されます。
また、ECサイトのページネーションは、検索エンジンのクロール効率とインデックス最適化に大きな影響を与えるため、適切な実装が非常に重要です。ページネーションがクロール効率とインデックスに与える悪影響は、以下の通りです。
クロールバジェットの消費
検索エンジンは、各サイトにクロールするページ数の上限(クロールバジェット)を割り当てています。
ページネーションが適切でないと、クローラーは価値の低いページ(例:フィルタリングやソートの組み合わせで生成される無数のURL)をクロールするためにクロールバジェットを浪費してしまう可能性があります。これにより、本来インデックスさせたい重要なページ(新商品ページなど)のクロールが遅れることがあります。
重複コンテンツと見なされるリスク
ECサイトのページネーションは、複数のページにわたって似たような商品リストが表示されるため、重複コンテンツと見なされるリスクがあります。
その場合、検索順位が下がるだけではなく、検索結果に表示されなくなる恐れがあります。また、ペナルティを受けていないページの順位も下がり、サイト全体での自然流入が減ることにつながりかねません。
リンク資産の分散
SEOでは、内部リンクや被リンク(外部サイトからのリンク)がページの評価を決定する上で重要です。ページネーションの各ページがリンクを集めてしまうと、本来評価を高めたいカテゴリページのリンク資産が分散されてしまう可能性があります。
このように、ECサイトにおいてページネーションは、ユーザーが求める商品を見つけやすくし、サイト全体の使いやすさを向上させるための、不可欠な機能と言えるでしょう。
ページネーションとSEO:最適化のポイント
ここでは、ページネーションの最適化方法について解説します。先項で解説したように、ページネーションが適切に実装されていないと、クロール効率の低下、重複コンテンツ、リンク資産の分散といった問題を引き起こす可能性があります。これらの問題を回避するためには、rel="canonical"タグの適切な使用や、サイト構造全体を考慮した慎重な実装が不可欠です。
なお、Googleは以前、ページネーションの連なりを伝えるためにrel="next"およびrel="prev"タグの使用を推奨していましたが、現在はこれらのタグをインデックスの目的では使用していないことを公式に発表しています。
上記の問題を解決し、ページネーションのSEO効果を最大化するために、以下の対策が推奨されます。
URLの正規化(Canonicalization)
重複コンテンツの問題を防ぐ最も重要な対策です。rel="canonical"タグを使用して、ページネーションの各ページが参照すべき「正規のURL」を検索エンジンに伝えます。
一般的には、ページネーションの各ページに自己参照のrel="canonical"タグ(例:2ページ目には2ページ目のURLを指定)を使用し、フィルタリングやソートによるパラメータ付きURLは正規化する、というアプローチが広く採用されています。
なお、example.com/products?page=2というURLに、rel="canonical"タグでexample.com/products(1ページ目)を指定する方法もあります。ただし、この方法は検索エンジンに2ページ目以降のインデックスを促さない可能性があるため、慎重な検討が必要です。
noindexの使用
価値の低いページ(例:ソート順を変えただけのページ)がインデックスされるのを防ぐために、noindexタグを使用する方法もあります。
ただし、安易にnoindexを使用すると、そのページに含まれる重要なコンテンツ(商品情報など)がクロールされず、インデックスされないリスクもあるため注意が必要です。
リンク構造の最適化
ページネーションのリンクは、検索エンジンのクローラーが次のページへ進むための道しるべとなります。
<a>タグを使い、各ページへのリンクを設置することが基本です。ユーザーエクスペリエンスの観点からも、最初のページと最後のページへのリンクを設置することで、ユーザーとクローラーの両方にとって利便性が向上します。
UXを高めるページネーション設計と代替UI比較
ECサイトの商品一覧ページにおける表示方法には、主に「ページネーション」「無限スクロール」「もっと見る」の3つがあります。それぞれに一長一短があり、サイトの特性やターゲットユーザーに応じて最適な方法を選択することが重要です。
ページネーション(Pagination)
ページを番号で区切り、ユーザーがクリックして移動する古典的な手法です。
メリット
・ユーザーの現在地が明確に
「10ページ中3ページ目」のように、ユーザーが全体の中でどこを見ているのか、あとどれくらいページがあるのかが明確にわかります。これにより、ユーザーは安心してサイトを閲覧できます。
・サーバー負荷の軽減
1ページあたりの表示件数を絞るため、一度に取得するデータ量が少なく、サーバーやデータベースへの負荷を抑えることができます。
・特定の商品を探しやすい
以前見た商品が何ページ目にあったか覚えていれば、ピンポイントでそのページに戻ることができます。
デメリット
・クリックの手間がかかる
ページを移動するたびにクリック操作が必要であり、ユーザーによっては煩わしく感じることがあります。
・UXの途切れ
ページの切り替え時に読み込み時間が発生するため、閲覧体験が中断されます。
無限スクロール(Infinite Scroll)
ページ下部までスクロールすると、自動的に次の商品が読み込まれて表示される手法です。SNSやニュースサイトでよく見られます。
メリット
・シームレスな体験の提供
ページ遷移がないため、ユーザーは中断されることなく、商品を次々と閲覧できます。
・エンゲージメント向上が期待
ユーザーが多くの商品を閲覧しやすくなるため、サイト滞在時間の延長や、想定外の商品との出会いにつながることがあります。
・操作が手軽
クリック操作が不要で、スクロールするだけでコンテンツが表示されるため、特にスマートフォンでの利用体験が向上します。
デメリット
・ユーザーの現在地が不明確に
ユーザーは全体で何件中何件目を見ているのか、把握しにくくなります。
・パフォーマンスの問題を引き起こす
大量のデータを一度に読み込むことで、ページの表示が重くなったり、ブラウザの動作が遅くなったりすることがあります。
・フッターへのアクセスが困難
ページをスクロールし続けると、フッターにある会社情報や利用規約などにたどり着くのが難しくなります。
・SEOへのデメリット
検索エンジンのクローラーは、JavaScriptで動的に読み込まれるコンテンツを完全にクロールできない場合があります。特にSEOを重視するサイトでは、対策が必要です。
もっと見る(Load More)
「もっと見る」や「続きを読み込む」といったボタンをクリックすることで、次の商品が同じページ内に読み込まれて表示される手法です。ページネーションと無限スクロールの中間的な性質を持ちます。
メリット
・ユーザーがコントロールできる
ユーザーは自分のペースでコンテンツを読み込むことができ、フッターにもアクセスしやすくなります。
・パフォーマンスを維持
必要に応じてコンテンツを読み込むため、無限スクロールよりもページの表示速度が安定しやすいです。
・UXとSEOのバランスが良い
ページ遷移がないためUXが良く、同時にページネーションのように各ページにURLを持たせることでSEOにも配慮できます。
デメリット
・クリックの手間がかかる
ページネーションほどではないものの、クリック操作が必要となります。
・コンバージョンへ悪影響
多くのユーザーがクリックせず、途中で離脱してしまう可能性があります。
・実装が複雑
ページネーションと比べて、JavaScriptを使った実装が必要になるため、技術的なコストがやや高くなります。
商品数が膨大で、SEOを重視したい場合や、ユーザーに特定の商品を探してもらいやすいようにしたい場合は、ページネーションが適していると言えるでしょう。
1カテゴリーに登録する商品数
ECサイトの1つのカテゴリーに登録する最適な商品数は、ユーザー体験(UX)、検索エンジン最適化(SEO)、サイトのパフォーマンスなど、複数の要素を考慮して決めるべきです。
なお、一般的には以下データのように2P以降への遷移率が低くなりがちなので、1P目に掲載する商品数や表示方法は重要性が高くなります。メインカテゴリーは、頻繁に並び替えなどメンテナンスをしましょう。
ルビー・グループデータ(平均値)
1P:遷移率100%(アクセス:10,000)
↓
2P:遷移率 約20%(アクセス:2,000)
↓
3P:遷移率 約70%(アクセス:1,400)
↓
4P:遷移率 約70%(アクセス:980)
※以降5P以降も遷移率は変わらず約70%で遷移
商品登録数を検討する際は。ユーザーが「このカテゴリーには十分な商品があるな」と感じつつ、ページネーションのページ数が極端に多くならないバランスが理想的です。
最適な商品数を決定するためのアプローチについては、以下を参照ください。
ユーザーの行動を分析する
Google Analyticsなどのツールを使用して、ユーザーが何ページ目まで閲覧しているか、どのページで離脱しているかを分析します。多くのユーザーが5ページ目や10ページ目で離脱している場合、そのカテゴリーの商品構成やページネーションのあり方を見直す必要があります。
商品分類を再検討する
商品数が多すぎるカテゴリーは、さらに細分化することを検討します。例えば、「レディースファッション」というカテゴリーの商品数が膨大なら、「トップス」「ボトムス」「アウター」のように、より具体的なサブカテゴリーに分けることで、ユーザーは目的の商品にたどり着きやすくなります。
フィルタリング・ソート機能の活用
ページネーションと合わせて、ユーザーが「価格順」「新着順」で並べ替えたり、「サイズ」「色」「ブランド」で絞り込んだりできる機能を充実させることで、商品数が多くてもユーザーが快適にブラウジングできるようになります。これにより、ページネーションの負担を軽減しつつ、品揃えの豊富さもアピールできます。
もっと見る・無限スクロールの検討
商品数が多いカテゴリーでは、ページネーションではなく、もっと見るボタンや無限スクロールの導入も有効な手段です。ただし、それぞれのメリット・デメリットを十分に理解した上で、サイトの特性に合った方法を選択する必要があります。
まとめ
ECサイトにおけるページネーションは、単なる技術的な機能ではなく、ユーザーに快適なショッピング体験を提供し、同時に検索エンジンから正しく評価されるために不可欠な戦略的ツールです。
ECサイトの設計段階で、ユーザーと検索エンジンの両方にとって最適なページネーションを慎重に設計・実装することが、ビジネスの成功に直結すると言えるでしょう。
ルビー・グループ株式会社は、ECサイトの構築、運用、コンサルティングを専門とする企業です。特にラグジュアリーブランドやファッションブランドのEC事業支援に強みを持ち、ECサイトのライフサイクル全般をワンストップでサポートいたします。
単にページネーションを実装するだけでなく、データ分析に基づいてユーザーの行動を深く理解し、その結果をデザイン・運用へと反映。ページネーションを単なるページ送り機能から、売上とユーザー満足度を向上させるための戦略的なツールへと昇華させることができます。ECサイトの構築や運営についてお悩みでしたら、ぜひご相談ください。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

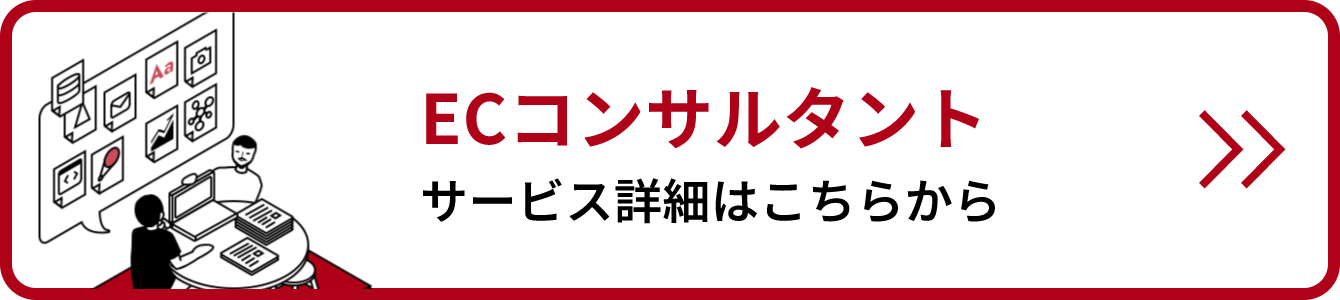
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





