
しかし、「自社サイトやブランドサイトで英語表記を多用しているが、ユーザー反応が良くない」「オシャレさを重視して英語を入れているが、意味が伝わっていないのでは?」と、不安や不満を感じている関係者の方は多いのではないでしょうか?
本記事では、英語を多用したWEBサイトが、ブランディングとユーザー体験に与えるマイナス影響について解説しています。
「英語を多用することがユーザー体験にどのような影響を与えるのか知りたい」「英語表記を変更する際のブランドイメージへの影響に不安がある」という方は、是非ご一読ください。
英語表記を多用するデザインの背景と現状

デザイン性・雰囲気
アルファベットは、日本語の漢字やひらがな、カタカナに比べて線がシンプルで、文字の高さや幅が比較的均一です。これにより、デザインに統一感と洗練された印象を与えやすくなります。特に、細めのフォントやミニマルなデザインと組み合わせることで、よりスタイリッシュに見えます。
また、アルファベットは文字自体の複雑さが少ないため、文字と文字の間や、文字と背景の間の余白(ホワイトスペース)が美しく見えます。これにより、ゆったりとした、高級感のあるデザインを演出しやすくなります。
このように日本語の漢字やひらがなと比べて、アルファベットはシンプルで洗練された印象を与えやすく、そのためスタイリッシュなブランドイメージを演出したいファッションやコスメ、ラグジュアリーブランドなどのWEBサイトのメニューやバナーに、英語が多用されているケースが多く見られます。
もちろん、欧米のサイトデザインに倣うことで、おしゃれな雰囲気を出す狙いもあります。
グローバル展開・多言語対応
海外市場を視野に入れている企業にとって、英語は共通言語として不可欠です。最初から英語表記を取り入れておくことで、海外のユーザーに自社の製品やサービスをアピールできます。インバウンド(訪日外国人観光客)の集客を目的としている場合も同様です。
また、「英語に対応している=グローバルに活躍している企業」というイメージを内外にアピールでき、企業ブランドの価値を高める狙いも。海外市場だけでなく、国内の顧客や優秀なグローバル人材を惹きつける上でも有効です。
技術的な側面
WEB開発の分野では、英語が技術的な共通言語として使われることが多いため、プログラマーやデザイナーがメニュー項目などを英語で記述する傾向があります。
また、多くのWEBサイトが利用しているCMSやECサイト構築サービスは、元々英語圏で開発されたものが大半です。これらのデフォルト設定やテンプレートは、英語のメニュー(例: "Home", "About", "Contact")を前提として作られています。テンプレートをカスタマイズする際も、元の英語表記をそのまま使用したり、少し手を加えるだけで済ませることが多いです。このように、日本語に全て置き換える手間を省くために、英語表記を多用する傾向も見受けられます。
以上のような背景から増えている英語表記を多用したWEBサイトは、ユーザーの混乱や、SEOへの悪影響を招くといった問題を引き起こしています。次項では、この問題について解説してみます。
英語多用がユーザー体験に与える影響
日本人ユーザーを主なターゲットとするWEBサイトでも英語表記が多用されており、それに伴って以下のような課題や問題が生じています。
ユーザーの混乱と離脱
英語表記は、一度頭の中で「これはどういう意味だろう?」と変換するプロセスを必要とします。このわずかな思考の遅れが、ユーザーにとってのストレスとなり、「このサイトは使いづらい」と感じさせてしまいます。
また英語に不慣れなユーザーにとって、英語表記ばかりのサイトは「このサイトは自分向けではない」と感じさせたり、メニューの意味が直感的に理解できず必要な情報にたどり着けない原因となったりします。特に高齢者層にとっては、大きなハードルとなり、サイトからの離脱率を高める可能性があります。
さらに、スタイリッシュなデザインを意図した英語表記が、かえって「敷居が高い」「自分には縁遠い」といったネガティブな印象を与えてしまうことも。親しみやすさや安心感を求める層にとっては、英語表記の多用は逆効果となる可能性が高いことを知っておきましょう。
SEO(検索エンジン最適化)への悪影響
Googleなどの検索エンジンは、ユーザーが検索に使用した言語と一致するサイトを優先して表示する傾向があります。例えば「coat」と設定していると、「コート」では検索にヒットしにくくなります。このように日本語で検索された場合、英語表記の多いサイトは関連性が低いと判断され、検索結果の上位に表示されにくくなる可能性があるので要注意です。
また、商品名やカテゴリ名を英語と日本語の両方で表記すると、キーワードが重複してしまい、検索エンジンの評価が分散される可能性があります。
さらに、サイト内の情報が英語ばかりだと、ユーザーは内容を理解しにくく、すぐにサイトを離れてしまいます。滞在時間の短さや離脱率の高さは、検索エンジンに「このサイトはユーザーにとって価値が低い」と判断される要因になります。
情報伝達の不確実性
デザイン性を重視しすぎて日本語表記を省略してしまうと、返品ポリシーや支払い方法といった重要な情報が不明瞭になり、ユーザーの不安を招くことがあります。
たとえば「Returns & Refunds Policy」といった英語表記だけでは、返品の条件(未使用品のみか、期間はいつまでかなど)や、返送料の負担といった詳細な情報が直感的に伝わりません。ユーザーは、重要な情報がどこに記載されているかわからず、購入をためらってしまうでしょう。
また「Free Shipping」という表記では、条件付き(例: 5,000円以上の購入で送料無料)であることが伝わりにくく、後からトラブルになる可能性があります。
こうした悪影響は、信頼性を高めるために正確な情報提供が不可欠なECサイトにとっては、致命的と言えるでしょう。
英語表記がユーザーに伝わらない具体例とその影響
ここでは、日本人ユーザーが直感的に理解しづらい英語表記の典型例と、その解決方法をいくつかご紹介します。
ナビゲーション(メニュー)
最もユーザーの混乱を招きやすいのが、サイトの根幹となるナビゲーションメニューです。
・表記例:About
・意図:「会社概要」「私たちについて」
・日本人ユーザーの反応:何のページかわかりづらく、問い合わせ先?ブランドの歴史?と迷ってしまいます。「About Us」となっていればまだしも、「About」だけでは抽象的すぎて意味が伝わらないでしょう。
・より良い表記:「会社概要」「ブランドについて」「私たちについて」など。
・表記例:My Account
・意図:「マイページ」「会員情報」「アカウント情報」
・日本人ユーザーの反応:WEBサービスに不慣れな層や高齢者にとっては、「Account」という言葉が馴染みがなく、何を指しているのか直感的に理解できません。
「My」とついているので、自分に関連する何かだとは推測できても、具体的な機能(購入履歴、住所変更など)が分からず、クリックを躊躇してしまいます。
また「Account」という言葉が、クレジットカード情報やパスワードなど、重要な個人情報が集約されている場所だと、漠然とした不安を抱かせることもあります。
・より良い表記:「マイページ」「会員情報」など。
商品ページ・購入手続き
購入に関わる部分は、特に正確な情報伝達が求められます。
・表記例:Add to Cart Add to Bag
・意図:「カートに入れる」「買い物かごに入れる」
・日本人ユーザーの反応:「カート」や「バッグ」という言葉は浸透していますが、「Add to ~」という表現に慣れていない人も多く、「Add」が「追加」とわからず、戸惑うことがあります。
・より良い表記:「カートに入れる」「買い物かごに追加」など。
・表記例:Checkout
・意図: 「レジへ進む」「購入手続きへ」
・日本人ユーザーの反応:英語に慣れている人でも、この単語が「購入手続き」を意味すると即座に理解できるとは限りません。「チェックアウト」というカタカナ表記でも、どの段階の手続きなのかが不明瞭です。
・より良い表記:「購入手続きへ」「レジに進む」など。
このように英語表記を多用しているECサイトのヒートマップやクリックデータを分析すると、以下のような傾向が見られます。
・英語表記ボタンはクリック率が低い
・意味が分からず、そのページでのイライラクリック率が高い
いずれも、ユーザー体験に対し悪影響を及ぼし、結果ECサイトにとって不利益をもたらすので、今からでも表記を見直すことをおすすめします。
英語と日本語を両立するためのデザイン改善ポイント
ECサイトで英語表記を使う場合の日本語併記ルールは、デザイン性とユーザビリティを両立させるために非常に重要です。明確なルールを設けることで、ユーザーの混乱を防ぎ、スムーズな購買体験を提供できます。
具体的には、以下を参考にしてみてください。
【基本ルール】日本語を優先し、英語は補助的に使う
原則として、サイトの主要なナビゲーション、購入手続きに関するボタン、法的な情報などは、日本語をメインとします(※)。
英語については、デザイン的なアクセントや、グローバルな雰囲気を出すための補助的な役割として使用します。(※メタタイトルなどSEOに重要な箇所はカタカナで設定)
具体的な併記ルール
1. 主要なナビゲーションメニュー
「商品カテゴリ」「会社概要」など、ユーザーが最初にアクセスする重要なメニューには、必ず日本語を使います。その隣に、小さく英語を併記すると、デザイン性を損ないにくいです。
例:
・商品一覧 / Products
・会社概要 / About Us
・お問い合わせ / Contact Us
2. 購入手続きのボタン
ユーザーが最も不安を感じやすい購入プロセスでは、直感的で分かりやすい日本語を最優先します。
例:
・カートに入れる / Add to Cart
・購入手続きへ / Checkout
・注文を確定する / Place Order
3. ページタイトルと見出し
ページタイトルや大きな見出しは、まず日本語で内容を伝え、その下に英文のキャッチコピーやサブタイトルを配置します。
例:
(大見出し)新着アイテム
(小見出し)New Arrivals
4. 法的情報・重要な説明文
利用規約、プライバシーポリシー、返品ポリシー、送料の説明など、法的な内容やユーザーが安心して取引するための重要な情報は、日本語のみで表記することを強く推奨します。
例:
・特定商取引法に基づく表記
・送料/配送について
・プライバシーポリシー
5. 補足的な情報・デザイン要素
メインのコンテンツではないものの、サイトの雰囲気を高めるための部分には、英語のみを使うことを検討できます。ただし、サイトの機能に影響しない範囲に限ります。
例:
・フッターのコピー: "© 2025 Your Brand All rights reserved."
・商品の画像: "Limited Edition" や "New Arrival" など、画像内のデザイン要素として英語を使う。
以上のように、ECサイトで英語表記を使う場合の日本語併記ルールは、「ユーザーが迷わないこと」を最優先に考えましょう。日本語をメインとし、英語はあくまでサイトのブランドイメージを補完するためのツールとして活用することで、デザイン性とユーザビリティを両立させ、ユーザーの満足度を高めることができます。
まとめ
日本語WEBサイトにおける英語表記の多用は、デザイン面の向上やグローバルなイメージを訴求できるというメリットがある一方で、ユーザーの利便性を損ない、情報が正確に伝わらないリスクもはらんでいます。
多くのサイトでは、これらのデメリットを考慮し、主要なメニュー項目には英語と日本語を併記したり、サイト全体のデザインとユーザビリティのバランスを慎重に検討したりする傾向が見られます。
ルビー・グループは、これまでファッションブランドに特化したEC事業の構築から運営までを一貫して支援してきました。特に、ラグジュアリーブランドとの取引実績が豊富であり、「Luxury brand × Technology」を掲げて、高い専門性を持つプロフェッショナル集団として事業を展開しています。
WEBサイトの制作や運営、ブランディングなどに関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

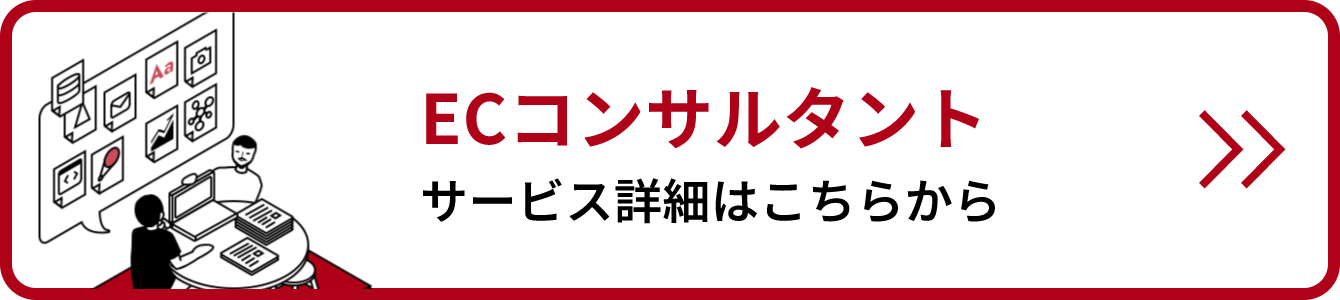
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





