
本記事では「バーチャル試着の導入がECサイトにもたらすメリットや、具体的な成功事例を通じた効果的な活用方法」について解説しています。
「バーチャル試着を活用することで購買意欲を高めたい」「導入に必要な技術や費用、サービスプロバイダーを調べたい」という方はもちろん、「バーチャル試着導入後の活用方法や、顧客体験をさらに向上させる施策を知りたい」という方も、是非ご一読ください。
バーチャル試着がEC業界にもたらす変化

まず、一般的な「バーチャル試着」の利用方法について、簡単に解説します。アプリなどを使い自分の画像をカメラで撮影、さらに商品の3Dデータを読み込みをすると自分の画像に商品画像が重なり、試着しているような3D画像になります。正面からだけでなく、横や背面からの画像の試着画像も確認することも可能です。
色やサイズだけでなく、実際に自分が着た時の雰囲気やサイズ感を確認できるのが「バーチャル試着」の特徴です。それでは、この「バーチャル試着」サービスを自社サイトに導入すると、EC事業においてどんな効果や変化が期待できるでしょう。
新たな顧客の獲得が可能に
従来のアパレル系ECサイトでは、実際に試着できないため、服のフィット感や具体的なイメージがわからず、多くの利用者から購入を避けられていました。しかし「バーチャル試着」のサービスを導入すれば、服を着た際のサイズやフィット感を確認できるため、今までECサイトでの購入を避けていた利用者層の獲得が可能になります。
また試着はすべてオンラインで行われるため、店舗に足を運ぶ時間がないユーザーでも、手軽に複数の服を試着することができ、ネット限定でしか買えない服も試着してから購入することが可能に。
さらに「バーチャル試着」は、大人・子供に関係なく利用できるサービスですので、これまで試着が苦手だったユーザー層にも、スムーズに試着をしてもらうことができます。
実店舗がないECサイトにとって、「バーチャル試着」の導入により、試着体験が提供できないという弱点を補えるだけでなく、これまで取り込めなかった顧客層の獲得が期待できるわけです。
返品率の軽減が期待できる
これまでECサイトの返品理由として多かったのが、「サイズが合わない」や「イメージと違う」といったものでした。しかし試着機能を導入することで、お客様が抱く商品イメージとのミスマッチを防げるため、返品を大幅に減らすことが可能になります。
返品率が低下すれば、返品対応にかかるコストが削減でき利益率の改善につながります。さらに、返品にかかる手間が大幅に減ることで、顧客サービスの充実やマーケティングへの注力など、他のリソースに時間を割けられるようになるでしょう。
データをマーケティングに活用できる
「バーチャル試着」を通じて得られるユーザーの行動データや、フィードバックを活用することで、自社のマーケティング戦略や商品開発に役立てることができます。例えば「試着商品の詳細情報(色、サイズなどのスペック)」や「商品ごとの試着率」などのデータを活用すれば、売れ筋商品の傾向予測ができるようになり、仕入数を調整するといったことも可能になります。
バーチャル試着が購買意欲を高める理由
ここでは、返品率低下の実現や購入時の安心感を提供する「バーチャル試着」が、顧客の購買意欲をどう向上させるかを解説いたします。
不安を軽減し、安心感を与える
消費者にとってバーチャル試着を利用する最大のメリットは、実店舗に足を運ばずとも実際の商品イメージを確認できる点です。また、すでに所有しているアイテムを着用した状態で利用すれば、ワードローブとの組み合わせを確認することもできます。
「この商品、自分に合うかな?」という不安は、お客様が購入をためらう理由の一つです。「バーチャル試着」を導入すれば、購入前に商品を試せるためお客様の安心感につながります。
例えばコスメの場合、色味や仕上がりを画面で確認できるので、「思っていた色と違った」というミスマッチを防げます。服やアクセサリーでも、自分に似合うかどうかを事前に確認できるため、購入に対する意欲が高まることにつながります。
コンサルティングファームのアクセンチュアが実施した、デジタルコマースへの効果に関するアンケート調査(※)では、ARなどの没入型技術を活用することで「商品が自分の期待した通りのものである」という確信が、世界全体では4%、米国に限って言えば9%も高まるということがわかりました。この結果は、「バーチャル試着」が消費者が購入前に感じる不安を取り除くことができる可能性が高いことを証明していると言えるでしょう。
※引用元:アクセンチュア レポート「Try it. Trust it. Buy it. 没入型技術が デジタルコマースの体験向上に貢献」
時間をかけずに無制限に試着を楽しめる
「バーチャル試着」なら実店舗までの移動時間が不要なため、自分の好きなタイミング・場所で商品を試せるので、忙しいユーザーでも時間を気にせずに商品を選べます。
また画面上で瞬時に商品を試すことができるため、着脱の手間も省けるので試着時間を削減できるというメリットも。時間が削減できれば色違いやサイズ違いなど、より多くの試着を気兼ねなく楽しむことができます。
またウェディングドレスや着物など、試着に時間がかかってしまうものをすぐに試せるのも大きな魅力です。
時間を気にすることなく沢山の試着を無制限に行え、色違いなども多く試しているうちにブランドの世界観に没入し、購入の障壁がグッと下がるわけです。
新しい自分を手軽に発見できる
「バーチャル試着」サービスがあれば、人前では試着することが恥ずかしいタイプの洋服や、普段は着用しない雰囲気やテイストのブランドを、自宅で気軽に試着できるという新たな体験価値の提供も可能に。いままで知らなかった自分を画面上で発見することもできます。
さらに、試着サービス画面に設置されているSNSボタンを押せば、試着している写真をSNSに簡単にシェアすることも。新しい自分を多くの友人にアピールすることで、購入意欲の向上に繋がります。
バーチャル試着の導入事例と成功のポイント
それでは事例をベースに、「バーチャル試着」の導入が、売上拡大や顧客満足度向上につながっているポイントを見ていきましょう。
JINS
ECサイトからWEBカムで撮影することで、実店舗と同じように自分が選んだメガネを試着することが可能。フレームカラーの変更、オプションレンズのお試し、メガネのかけ位置調整やPD値(左右の瞳孔の中心間の距離)のチューニングもできます。
JINSオリジナルAIが顔型を測定し、試着したメガネの似合い度を判定。気に入ったメガネがあれば、ECサイト内からそのまま購入できます。
なお、アプリにJINSの店頭で購入したメガネの保証書やレンズの度数情報を登録しておくと、同じ度数のメガネを注文することも。
実際に試着してみないと似合っているのか判別しづらいメガネですが、JINSの「バーチャル試着」サービスを利用することで、自宅にいながら自分に似合っているのかの確認が可能に。さらに、お似合い度を表示することで購入意欲を後押しする仕組みになっています。
MIKIMOTO
各商品ページの「試着する」ボタンをタップすると、スマートフォンのカメラを使ってさまざまなジュエリーの試着が可能に。ブローチは付ける位置や角度を変えながら着用イメージを確認できるほか、リングは重ねづけのシミュレーションまで楽しむことができます。
またパソコンを利用している場合は、商品画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み込むことで、自身の写真を使った試着が可能に。
ピアスのような、衛生面において試着が敬遠されやすい商品に関しても、「バーチャル試着」により気軽に体験できるようになり、顧客満足度の向上や売上げの増加に貢献。また、敷居が高い高級宝飾品をスマホで気軽に試着できるようにすることで、若年層へのアピールに成功しています。
PAL CLOSET
「バーチャル試着体験」ページには全24アイテムが設置されており、利用者はスマホ上でそれぞれのスナップコードをタップし、スマホのカメラを自身に向けることで、実際に試着したイメージに近い形でのバーチャル試着を体験できます。また、複数あるカラー展開にも対応し、簡単な操作でその場で自分に似合うカラーを見つけることも可能に。
実際の洋服のパターンデータを元に制作した3DCGをアプリ内に表示できる形に変換して作成しているため、360度どこからでもアイテムの雰囲気を確認できるところが成功のポイントです。
バーチャル試着を支える最新ソリューションの紹介
バーチャル試着の精度が大きく向上したのは、AI技術の進化がきっかけです。AIにより、消費者一人ひとりの体型や寸法に合わせたシミュレーションや、自宅にいながら実店舗並みに洋服のサイズ感などを確認できるようになりました。
近年ではAI以外にも様々な技術の進化が目覚ましく、「バーチャル試着」は新しいステージに入ったと言えます。ここでは「バーチャル試着」を支える最新ソリューションをご紹介します。
アプリが無くてもバーチャル試着が可能「アプリレスAR」
「アプリレスAR」は、専用アプリをインストールすることなく、ウェブブラウザ上でAR(拡張現実)を体験できるサービス。ECサイト上に掲載されているQRコードをデバイスで読み取るとARカメラが起動し、画面上に写った自身の姿に商品のデータを重ねると「バーチャル試着」が可能になります。
専用のアプリが不要なため、アプリのインストールや操作に不安がある方でも、気軽にバーチャル試着を楽しめる点が最大の特徴です。
採寸をしなくてもおすすめのサイズを提示「AIサイズガイド」
米国で主流となっている「AIサイズガイド」は、採寸をする必要はなく、質問に答えていくという会話型ユーザーエクスペリエンスを使用したフィット調査。
従来のサイズガイドと根本的に異なるのは、先に採寸をして洋服に当てはめるという考え方ではなく、個人によって異なるフィット感を重視している点。
身長、体重、年齢という基本情報を入れて、バストやウエスト、ヒップ、首、太ももなどのフィット感の好み(ゆったりしているのが好き、ピッタリしているのが好き、など)を選び、愛用しているブランドとサイズを答えると、その商品のおすすめサイズが分かるというわけです。
自分のサイズのデータを保存しておけば、商品ごとにおすすめサイズが提示。Mサイズの人でも、大きめにできているアイテムではSがおすすめサイズとして提示されるという柔軟性も備えています。
採寸の正確性に自信がないユーザーでも、おすすめのサイズを提示してもらえる気軽さが、多くのECサイトで導入されている理由です。
着用時にきつい部分を示してくれる「3Dバーチャル試着」
ソフトバンクと大手繊維商社のMNインターファッションが共同で開発をしている「3Dバーチャル試着」は、既存のサイズレコメンドに特化した「バーチャル試着」とは異なり、リッチな試着体験をオンラインで提供が可能です。
3DCGで作成したアバターを用いることで、洋服のコーディネートを360度いろんな角度から確認可能。試着するアバターの髪型や肌色も変えることができるので、ヘアスタイルやメイクを変えた際の「バーチャル試着」も楽しむことも可能になります。
また、アバターを動かして洋服の動きを確認することも。消費者の体型に合わせて、服のシワや陰影、シルエットをリアルタイムで表示することができるため、日常の動作の中でどういった見え方をするのかを客観的に確認できます。
さらに、着用時にきつい部分をヒートマップで示すことも可能に。アバターの体型に合わせて肩の周りがきつかったり、お腹周りがきつかったりということを視覚化することができるそう。
今後の研究によっては、シミュレーション技術を活用して、1歳の子どもが半年後にどのくらいのサイズの服が合うかを確認することもできるということ。「ダイエットして10キロ痩せたらこの服が着られるか」などの確認をすることも可能になるかもしれません。
【まとめ】バーチャル試着で変わるEC体験 ~購買意欲を高める最新機能と導入事例~
「バーチャル試着」は、実際の着用感がわかりやすくコーディネートもイメージしやすいため、購入率アップ・返品率の減少につながることが予想されます。また、これまでECサイトでの購入を避けていた消費者層の獲得も可能にします。
その一方で、「システム導入費用が高い」「アパレルデータを定期的に取得・更新する必要がある」といったデメリットが挙げられます。
また実物を触ったり見たりすることができないため、問い合わせの増加につながる可能性もあり、そうしたケースを避けるために、商品情報を細かく記載するなど、ユーザーが理解しやすいデータを提供する手間が発生します。
「バーチャル試着」システムを導入する際は、メリット・デメリットをしっかりと確認し、十分に検討をしましょう。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!




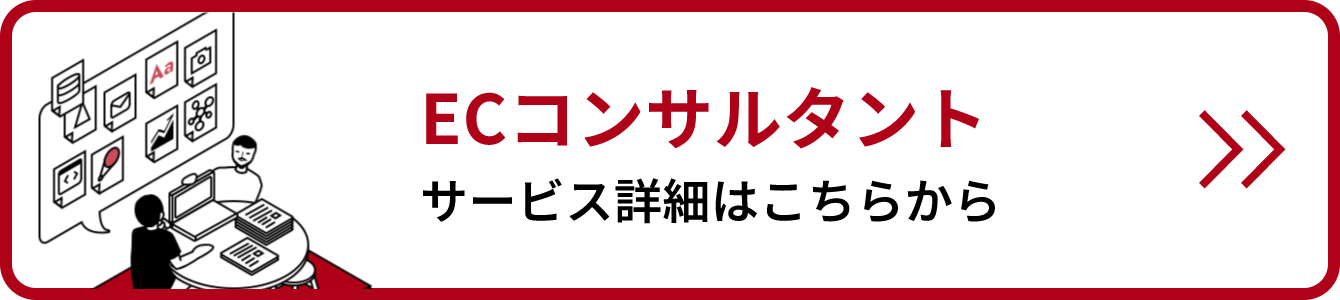
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly
