
日本においてもOMOマーケティングに取り組む企業が増えていますが、その一方で「何から取り組めば良いか分からない」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
本記事では、近年注目されている新たな概念の成功事例や、、どのように活用できるかなどの事例などを紹介、OMOマーケティングの基礎と最新動向について解説しています。
「OMOマーケティングの定義と特徴について知りたい」「OMOとオムニチャネルの違いとは?」という方はもちろん、「OMOを導入する際の課題(データ統合、社内リソース、コスト)は?」「他のマーケティング施策(ライブコマース、越境EC)と、どのように連携できる?」という方も、ぜひご一読ください。
OMOマーケティングとは?オムニチャネルとの違い

OMO(Online Merges with Offline)マーケティングとは、オンラインとオフラインの垣根を取り払って融合し、シームレスで良質な顧客体験を提供するマーケティング手法です。
これまでも、インターネットでクーポンを配布して実店舗に誘導する、あるいは実店舗でチラシを配布してECサイトに誘導するなど、オンラインとオフラインを結びつけた取り組みは各企業で行われてきました。
しかし、オフラインとオンラインはあくまで別のチャネルとして捉えられていました。それに対し、OMOマーケティングは「オンラインとオフラインの区別がない、完全なる融合」という考え方をベースにしています。
オンラインとオフラインの連携という点で、近いマーケティング手法として「オムニチャネル」があります。
オムニチャネルとは、実店舗、ECサイト、SNS、コールセンターなど、企業が持つあらゆるチャネル(販売経路)をどのようにして連携させるか、顧客情報や在庫情報をどう一元管理するかを考える戦略です。
そういう意味ではオムニチャネルもまた、オンラインとオフラインの融合を意識したマーケティング手法と言えます。
ただしオムニチャネルが、販売する側の視点でデータを活用して顧客に購買を促すものであるのに対し、OMOマーケティングは顧客側の視点で「ユーザーエクスペリエンス(UX)」を向上させることを主目的にしています。
顧客が好きな方法で購入でき、購買前の検討段階から購買後にいたるまでのすべてのフェーズにおいて顧客体験を向上させることにフォーカスしているのがOMOマーケティングなのです。
OMOマーケティングが注目されている背景には、消費者の心理や行動の変化があります。
ECサイトやスマートフォンが普及し、商品をいつでもどこでも購入できるのは当たり前になりました。またSNSの普及により、誰でも気軽に情報を発信できるようになり、口コミなどを参考にする人が増加しました。
こうした時代の変化により、現代の消費者は、商品やサービスの価格や機能など物理的な価値観だけでは満足できなくなり、購入した商品やサービスを通して得られる満足感など、心理的価値観までも重視する傾向にあります。
そのため現代のマーケティングの世界では、購入前から購入後にいたるまでの顧客体験を向上させることが、売上拡大や企業価値を高めるのに不可欠だと考えられています。
OMOマーケティングの成功ポイント|データ活用と顧客体験の向上
それではここで、OMOマーケティングを活用して売上を伸ばすためのポイントをご紹介します。
データ統合環境整備とパーソナライズ体験の提供
OMOマーケティングの提唱者である元GoogleチャイナのCEOのカイフ・リー氏は、OMOを推進するにはモバイルアプリ、スムーズな決済システム、高品質で低コストのセンサー、AI技術が不可欠であると述べています。
OMOを実現するには、複数のICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の活用が必要になります。なかでも、オンラインとオフラインのデータ統合・分析は不可欠。
自社のすべての販売チャネルの商品・顧客データを一元管理し、集約したデータの分析結果を商品やサービスに反映させるために、CRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援)などのツールを駆使しましょう。
さらに、オンラインでの顧客行動データ(ECサイトの閲覧履歴および商品購入履歴など)をもとに、オフラインでもパーソナライズされた体験を提供することで、顧客が自身に寄り添ったサービスをどこでも受けられるようにすることも欠かせません。
じっくりとPDCAサイクルを回せる体制の構築
インターネットやSNSの普及により、ひと昔前と比べると企業と消費者の接点は多くなりました。OMOマーケティングでは、実店舗やECサイトだけでなく、SNSやチャットなど様々な販売チャネルを通じ、あらゆる角度から消費者の購買データを収集・分析し、消費者により良い顧客体験を提供するための、PDCAサイクルを回すことができる環境が求められます。
しかし、簡単に成果が出ない大規模なプロジェクトになりがちだからこそ、各部門部門が密に連携し、トライ&エラーを繰り返しながら、一歩ずつ理想像へと近づくような取り組みができる体制の構築が必要になります。
ICTを活用したリアル店舗の環境改善
OMOマーケティング先進国・中国のとある小売店舗では、顧客があらかじめアカウントを作成し顔認識情報を登録しておけば、商品をセルフレジに置くだけで、スマートフォンを取り出すことなく顔認証を通じて決済を行えます。
また靴ショップでは、興味のある靴を手に持つと商品情報がモニターに表示され、タグをスマートフォンでスキャンすればそのままECサイトで購入できるように。
日本においても、アパレル企業では、店頭での試着をECサイトから予約できる環境を構築しています。
また、とあるスーパーマーケットでは、商品棚に陳列されている食材のQRコードをスマートフォンで読みこむと、産地や店舗までの流通経路などのサプライチェーン情報までも提供。消費者に食品の安全性や信頼性を提供しています。
このようにOMOマーケティングでは、消費者の視点でオンラインとオフラインを融合した良質な顧客体験の提供が求められます。それだけに、ICTを活用したリアル店舗の環境改善もまた、避けて通れない施策と言えます。
最適な人材の育成とアサイン
OMOマーケティングを推進するうえで真っ先に着手したいのが、シームレスで良質な顧客体験の設計です。
OMOの実現によってサービスやブランドが提供できる顧客体験や、それによって発生するビジネス上のメリットをしっかりと見定めることが求められます。そのためにも、プロジェクトの担当者には顧客目線で商品やサービスの改善策を立案できる能力が必要になります。
また、様々な販売チャネルに精通し、WebマーケティングやICTの知識を有し、データの活用方法に関する企画力と実行力がある人材でなければなりません。
さらに、複数部門の担当者と連携するため、社内で調整力や交渉力を持っていることも重要です。
こうした人材を育成し、アサインすることがOMOマーケティングを成功させるための重要なポイントになります。
OMOマーケティングの成功事例|日本・海外の先進企業の取り組み
次に、OMOマーケティングを実践し、成功している国内外の企業の事例をご紹介します。OMOマーケティング成功の秘訣を学んでみてください。
ユニクロ「ORDER & PICK」
スマホアプリやECサイトをベースに顧客とつながり、顧客がオンラインとオフラインを行き来できる環境を整えています。その一環となる施策が、2023年10月から本格展開している、スマホで購入した商品を2〜3時間後に店頭で受け取れる「ORDER & PICK」です。
「仕事や学校帰りに最寄りの店頭で商品を受け取りたい」「商品探しはアプリでゆっくりと、受取りは店頭ですぐに」「オンラインストアに在庫がない商品を、店頭でキープしたい」といったニーズに応える仕組みして提供しています。
オンラインでの利便性を活かしつつ、来店促進することで、顧客体験と売上の向上に寄与。実際、店頭で他の商品に触れる機会を増やし、「なんとなく気になっていた商品を、ついでに買ってしまう」という体験を、利用者に提供しています。
青山商事「DIGI-lab」「TAP&FIT」

店頭にある商品に加え、ネットを使って全国約700店舗の在庫から商品を探すことを可能にしています。利用客は採寸といった店舗ならではのサポートも受けられる上に、購入商品を自宅に無料配送してもらうことも。
さらに、オンラインショップの商品を最寄りの店舗に取り寄せて試着できる「TAP&FIT」も展開。「ネットで見つけた商品が店舗になかった」「サイズ感がわからないまま購入するのは不安」といった、オンライン・オフラインそれぞれの顧客の悩みやトラブルを、OMOマーケティングによって解決しています。
日本マクドナルド「モバイルオーダー」
テーブルデリバリー対象店舗では「席で受け取る」を選択すれば、スタッフが席まで注文商品を運んでくれます。
ファーストフード店では、注文するまでに時間がかかったり、レジ前で商品の受け取りを待たされることも珍しくないため、「注文時の行列に並ばなくて済む」だけでなく「駐車場でも受け取れる」などの新しい体験を顧客へ提供。気軽かつスピーディに利用できるファストフードの特徴を進化させた、OMOマーケティングの事例といえるでしょう。
アリババ「盒馬鮮生(フーマーフレッシュ)」

利用客は、陳列された商品のバーコードをモバイルアプリで読み取ることで、価格だけでなく在庫数や、産地などの情報を確認可能。無人レジで商品をスキャンし、基本的にモバイルペイメントで支払いをします。また、店舗でスキャンした商品をすぐさま自宅へ配送してもらうことも可能です。
さらに、オンラインで注文した食材を使った料理を店内レストランで食べたり、過去に店舗で購入した商品を購入履歴からオンラインで注文することも可能。まさに、オンライン・オフラインの垣根をなくしたシームレスな購入体験を、様々な切り口で顧客に提供しています。
OMOマーケティング導入の課題と今後の展望
OMOマーケティングを実現しようとすると、組織全体で越えなければならない数多くの障壁が目の前に立ちはだかります。ここではOMOマーケティングを導入する際の、主な課題を取り上げてみたいと思います。
システムの統合と、セキュリティ対策の徹底
たとえば、リアル店舗で使っているPOSや販売管理システムは、在庫管理を一定時間ごとのバッチ処理で行うのが一般的です。一方でECサイトの在庫管理は、リアルタイムで行うのが原則です。このように処理や管理の方法が異なるシステムをどのようにつなぐのか。在庫管理ひとつをとっても、システムの制約がOMOマーケティング実現の妨げになることがあります。
さらにOMOマーケティングでは、お客様がいつでもどこでも買える環境を作るために、店舗で欠品している商品をEC在庫から発送する、ECで在庫がない商品は店舗在庫を取り寄せて発送するなど、「今どこに在庫がどれだけあるのか」を可視化し、その在庫を店舗・ECサイト間でシームレスに動かすことができるシステムの実現が求められます。
また、顧客の個人情報を含むデータを扱う際には、プライバシー保護とセキュリティ対策を徹底することも重要。顧客の同意を得た上でデータを収集し、適切なセキュリティ対策を講じてデータ管理をする必要があります。
相応の初期コストが必要になる
OMOマーケティングは、シームレスな顧客体験の提供により売上を目指しますが、顧客を満足させる体験を提供するためには、相応のコストが必要です。
アプリや、実店舗とECサイトのデータを統合するための開発費用など、多大な初期コストが必要になります。
またOMOマーケティングは、顧客データを基点とした顧客体験の向上を行うために「データを運用できる人材」も必要です。もちろんECや店舗、物流、システムなどを横断的に理解していることも重要で、そうした人材を外部から採用するか、自前で育てる必要があります。
OMOマーケティングを進めるには、時間・費用・人材といった初期コストがかかるため、自社で開発・運用できるリソースがない場合は実現が難しいとお考えください。
組織や評価制度の見直しの着手へ
社内の各部門が縦割りの業務を続けていれば、OMOマーケティングの推進にブレーキがかかります。OMOマーケティングを実現するためには、関連部門を横串し、常に全体最適で考える必要があります。
そのためには経営トップ層が陣頭指揮を取り、OMOマーケティングを推進するための組織体制や評価制度の見直しなどを行うことも必要でしょう。
まとめ
OMOマーケティングに取り組むためには、業界全般の知識を有するだけでなく、ECやIT、店舗のことも理解しているプロジェクトマネージャーやリーダーの存在は不可欠です。しかしこうした人材は希少であり、採用しようと思っても現実的ではありません。
ルビー・グループでは、これまで多くのラグジュアリーブランドのEC構築、フルフィルメントサービスの提供、マーケティング、オペレーションを手掛けてきており、様々な課題に対して、デジタルテクノロジーを駆使したソリューションをご提供しています。
Eマーケティング、Eコマース、デジタルファッションの経験を持つメンバーだけでなく、大手アパレルにて、ファッションブランドのマーチャンダイジングを経験し、日本のファッションビジネスに対する幅広い知見を持ったメンバーも揃っています。
クライアントの目指すべき成長の未来像を意識し、OMOの視点からオンラインのみでなく、オフラインも含めたコンサルティングを心がけ、パートナーとして並走させていただきますので、OMOマーケティングでお困りであれば、ぜひルビー・グループにご相談ください。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!



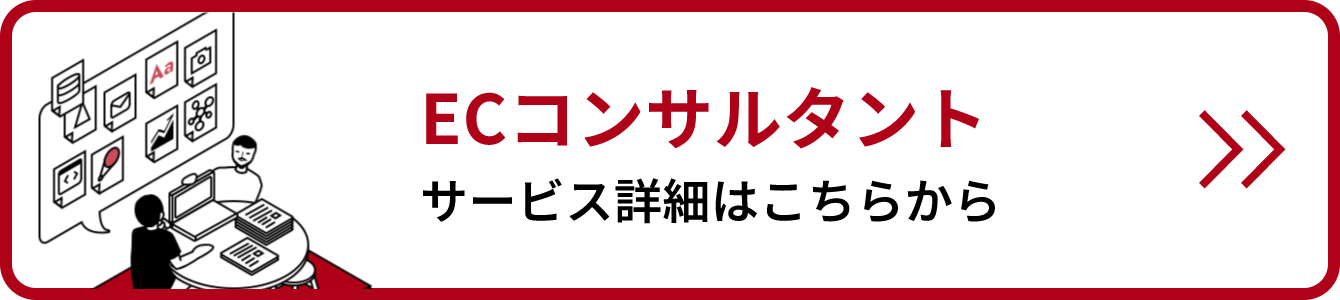
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





