
特に最近では、小紅書(RED)の公式アカウントが、企業HPと同様の立ち位置にあるなど重要な地位を傷ています。
本記事では、小紅書(RED)に関する基本的な情報や、日本企業が利用するメリット、活用方法や注意点などを詳しく紹介しています。
「中国向け越境ECを始めたものの、効果的なSNS施策が分からない」「企業が小紅書を活用するメリットと具体的な方法について知りたい」という方はもちろん、「越境ECプラットフォームや中国現地の代理店との連携方法について検討している」「小紅書のWeChatやWeiboとの違いや併用戦略について調べている」という方も、ぜひご一読ください。
小紅書(RED)とは?ユーザー層と特徴を解説

SNSとECの機能が融合したプラットフォーム
小紅書(RED)は、「世界中の良いモノが見つかる」をコンセプトに中国で開発されたソーシャルプラットフォームです。
主にライフスタイルや美容、コスメ、ファッション、旅行、グルメなどの情報を共有する場として知られ、一種のコミュニティを形成しています。
ショートムービー・写真・テキストが投稿できるSNSであるという点でInstagramと似ていますが、投稿にリンクを貼って商品の購入が可能であるなど、EC機能も備えています。
もともとホワイトカラー層などの購買力のあるユーザーが、自身が買った魅力的な商品の写真を投稿。その投稿を見たユーザーが商品に興味を持ってECサイトで購入に至るケースが多かったことから、2014年にECカートの機能を追加。ユーザーが投稿したコンテンツに、商品のリンクを貼れるようにし、アプリ内で決済まで完結できる仕様になっています。
投稿された膨大なコンテンツは、高度なAIシステムによりパーソナライズされたレコメンデーションが行われ、また、タグを軸に特定商品のレビューが検索しやすいよう設計されています。
そのため、小紅書(RED)では、「投稿を見て商品を知る」(商品認知)→「商品名で検索し口コミをチェック」(検討)→「小紅書(RED)内のEC機能で買う」(購入)までが、アプリ内で完結できるという特徴があります。
30歳未満の女性を中心に3億人が利用
現在、約3億人のアクティブ ユーザー(男女比は3:7)がいるとされ、大多数は中国本土に集中し、さらに約7割が一線城市と新一線城市という大都市に住んでいます。また、全ユーザー数のうち1995年以降生まれが50%、2000年以降生まれが35%となっています(※)。
(※)参照元:https://www.qian-gua.com/blog/detail/2898.html
「リアルな体験共有」に価値を置いたアルゴリズム
中国では何かを調べる時、検索エンジンよりもSNSが使われることが多く、小紅書(RED)も例外ではありません。
そのため多くのユーザーはレビューやハウツー形式での投稿を行っており、信頼性の高い情報をシェアすることが評価されやすい傾向にあります。
また小紅書(RED)は「リアルな体験共有」に価値を置き、ブランドよりもコンテンツの質を優先するというアルゴリズムを採用しています。
新しく作られたアカウントが投稿したコンテンツでも、ポスト直後は既存アカウントと同等の表示数が与えられ、その後は、獲得したシェア数>コメント数>保存数>いいね数の割合でつけられたスコアを基準に、表示回数や表示順位が決まります。
これにより、商業的な投稿は排除され、ユーザーにとって有益である誠実な投稿が優先されるのと同時に、中小企業や個人の商品もユーザーに見つかりやすいという特徴を持っています。
昨今のSNSでよく見られる「一部インフルエンサーや企業の投稿ばかりがピックアップされる」といった事象が起きにくい仕組みになっているところが、他のSNSと大きく違う点と言っていいでしょう。
このように小紅書(RED)は、多くのユーザーの消費意思決定プラットフォームとして中国での商業的価値が高まっています。
なお、最新版の小紅書(RED)アプリは翻訳機能を搭載しており、日本語で内容を閲覧することも可能です。日本からも利用することができ、日本企業のプロモーションにも活用されているので、ぜひ参考にしてみてください。
企業が小紅書を活用する3つのメリット
次に、日本の企業が小紅書(RED)をマーケティングに活用するメリットについて解説します。特に越境ECの売上拡大を狙っている方や、インバウンド集客の強化を考えていらっしゃる方は、ぜひご覧ください。
1. インバウンド集客を促進
小紅書(RED)は中国発のアプリではありますが、中国本土だけでなく、台湾、マレーシア、香港、シンガポール、日本で暮らす中華系のユーザーに利用されています。
そのため小紅書(RED)を活用してマーケティング施策を実施すると、中国本土だけではなく、中華圏や東南アジアなど、幅広いエリアでの効果が期待できます。
また、小紅書(RED)のユーザーには日本に関心が高い層が多く存在し、日本旅行や観光に関する情報交換が活発に使われています。このようなユーザーに対して日本での買物情報や観光情報を発信することで、購買意欲が高い中国系観光客のインバウンド集客を促進することができます。
2. 越境ECの売上増加
中国への越境ECの手段として、現地のECサイトに登録する手段が最もメジャーですが、それだけではプロモーションや発信力が足りず、そもそも見向きされません。
小紅書(RED)はEC機能も備えており、海外からの商品販売も可能です。また、自社ECサイトなどへの誘導することもできます。
さらに最近では、他アプリとシームレスな連携をするなど、日本のEC事業者にとってより障壁が下がっていると言えます。
小紅書(RED)をマーケティングに活用すれば、効果的に中国国内で自社商品を紹介し、越境ECでの売上増加に繋げることができます。
3. 高いエンゲージメント率
小紅書(RED)はコミュニティ性が高く、ユーザー同士の交流が活発です。そのため、投稿に対するエンゲージメント(いいね・コメント・シェア)が高く、口コミ効果が期待できます。また、こうしたユーザー投稿を資産として蓄積できるのも魅力的なポイントです。
さらに、商品のタグ付け機能が充実していて、特定の商品のレビューや情報を見つけやすくなっているため、ユーザーが商品に関する情報を効率的に収集しやすく、広告以上にユーザーの購入意欲を高める効果が期待できます。
小紅書マーケティングの成功パターンと注意点
ここでは、小紅書(RED)で中国版インフルエンサーを使ったマーケティングをする際の注意点や、投稿をバズらせるための基本について解説していきます。
中国版インフルエンサーと自社ブランドとの相性を見極める
ユーザーに対して影響を与えるユーザーのことを日本ではインフルエンサーと呼びますが、中国では「KOL」「KOC」がそれにあたる存在になります。
「KOL」(Key Opinion Leader)は、特定の分野に精通し、一定の専門性と信頼性をもつユーザーで、影響力の大きい順位に、トップKOL(フォロワー数100万以上)、ミドルKOL(フォロワー数10-100万未満)、マイクロKOL(フォロワー数10万未満)と、3種類にランク付けされています。
コラボレーション・パートナーとしてKOLを選定する際のポイントは、自社ブランド・商品との相性を見極めることです。
KOLによって得意とする分野やフォロワー、影響を与えることができる層がそれぞれ異なるので、フォロワー数や実績だけではなく、フォロワーの年齢層・所得層などの確認も必ずしましょう。
「KOC」(Key Opinion Consumer)は、あくまで消費者としての立場で発信し、一定の影響力を持っているユーザーを指します。フォロワー5000人前後のアカウントも多く、より消費者に近い感覚で発信をしていることから、実際に購入をする際は「KOL」よりも「KOC」のレビューを参考にするというユーザーも少なくありません。
最近の中国では、認知度を上げるために、最初にトップKOLやミドルKOLを使い、認知度を上げた後は、中国消費者により近い存在であるマイクロKOLやKOCを使って中国市場を攻めていく、という戦略が多くのブランドで採用されています。
なお費用については、KOLのランクや依頼する内容などによって変わりますが、小紅書(RED)の場合は「約2円~/フォロワー」が相場です。フォロワーが多くないマイクロKOLやKOCでしたら、謝礼1万円以内で済むケースもあります。
なお、KOLの選定・手配やマーケティングサポートまでを行うMCN(マルチチャンネルネットワーク)会社に委託する場合は、数百万円〜することがあるのでご注意ください。
ハッシュタグや高画質の画像を駆使したブランドストーリーを展開する
小紅書(RED)ユーザーの多くは、商品そのものだけでなく、ブランドの理念やストーリーにも関心を持っています。
たとえばユニクロは、「#持続可能なファッション」や「#日本の快適スタイル」といったハッシュタグを用いて商品を紹介すると同時に、「シンプルで快適な生活」をテーマにしたコンテンツを小紅書(RED)で展開。ブランドへの共感を高めることに成功しています。
また、小紅書(RED)でこれまで人気を集めた投稿の多くは、高画質な写真や動画を駆使しており、商品の魅力が一目で伝わる内容となっています。特に、「日本の美」を強調した高画質なビジュアルは、中国のユーザーから多くの「いいね」やコメントを獲得しています。
ハッシュタグや高画質な画像や動画を駆使したブランドストーリーを軸にしたマーケティングは、小紅書(RED)上でユーザーとの感情的なつながりを築くのに効果的であり、長期的なブランド価値の向上につながります。
小紅書を活用した集客・販売導線の設計法
それではここで、小紅書(RED)を使ったマーケティングの手順や、有効な導線設計方法についてご紹介します。
口コミづくりと露出の拡大
ターゲット層となる消費者が小紅書(RED)上で検索をしても、口コミがなければ発見してもらえません。企業公式の情報発信の場となる公式アカウントを開設して情報を発信するだけでなく、信頼性の高いKOCを活用してモニター体験、来店体験を実施。消費者目線からの口コミ情報を小紅書(RED)上に発生させましょう。
ECサイトへの導線確保
小紅書(RED)で話題になった自社商品を購入してもらうために、中国版インフルエンサーである「KOL」「KOC」に、自社ECサイトのURLを紹介してもらうという手法がありますが、昨今、注目を集めている「WeChatミニプログラム」を利用する方法もあります。
中国で絶大な人気を誇るチャットアプリ「WeChat」の中で動くサービスで、ユーザーはアプリのようにダウンロードする必要がなく、WeChatのプラットフォーム内で、そのまま簡易版のアプリプログラムが利用できることから、ミニプログラムと呼ばれています。
このプログラムを利用して中国市場向けのECサイトを展開できるのですが、最大のメリットは販売手数料は1%以下と、ミニマムな費用で越境ECを始めたい企業にとって、ハードルが低く、開始しやすい設定になっている点にあります。
小紅書(RED)でインフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらい、そのインフルエンサーのプロフィールや投稿に、WeChatミニプログラムへのリンクを貼ってもらうことで、ユーザーをミニプログラムに誘導することが可能になります。
また、小紅書(RED)で特定のハッシュタグを付けて投稿すると、WeChatミニプログラムで割引クーポンが発行されるなど、連携したキャンペーンを実施することで、ユーザーのエンゲージメントを高めることができます。
その他にも、小紅書(RED)では、アリババが運営するECプラットフォーム淘宝(タオバオ)傘下の天猫(Tmall)と、「紅猫計画」と称する戦略的協業を実施。コンテンツから購買へのシームレスな接続を実現しています(参照:https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/05/84be8475f9ba94c5.html)。
訪日前の情報発信と、訪日中の店舗誘導
小紅書(RED)で話題になった自社商品を、国内店舗で購入してもらうために、訪日を計画している中国人観光客に向けて積極的に情報を発信しましょう。
さらに、自社リアル店舗への誘導を促進するためにするために、訪日中のユーザーに小紅書(RED)の地図タグを積極的に利用してもらいましょう。
地図タグは、投稿に場所情報を追加できる機能で、ユーザーが投稿した場所を他のユーザーに共有したり、特定の場所の投稿を見つけたりするために使われます。投稿に地図タグを追加することで、投稿のエンゲージメントを高め、より多くの人にリーチさせることができます。
まとめ
小紅書(RED)は、訪日中国人や中国本土ユーザーに対する認知獲得に有効なSNSです。現在は、女性に人気の化粧品やファッションなどのトレンド情報だけでなく、出産、育児教育などの生活情報や、旅行、食べ物、日常のライフハックに関する情報など、あらゆる人の関心事をシェアできる場所になっています。
また、多くの人が商品購入時の参考にするため、他者のレビューや企業の発信をチェックするなど、情報の検索サービスとしての役割も強まっています。
さらに、小紅書(RED)を活用してマーケティング施策を行えば、中国本土だけではなく、中華圏や東南アジアなど、幅広いエリアでの効果が期待できます。
越境ECやインバウンド集客の強化をお考えなら、小紅書(RED)を活用したマーケティング手法に積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

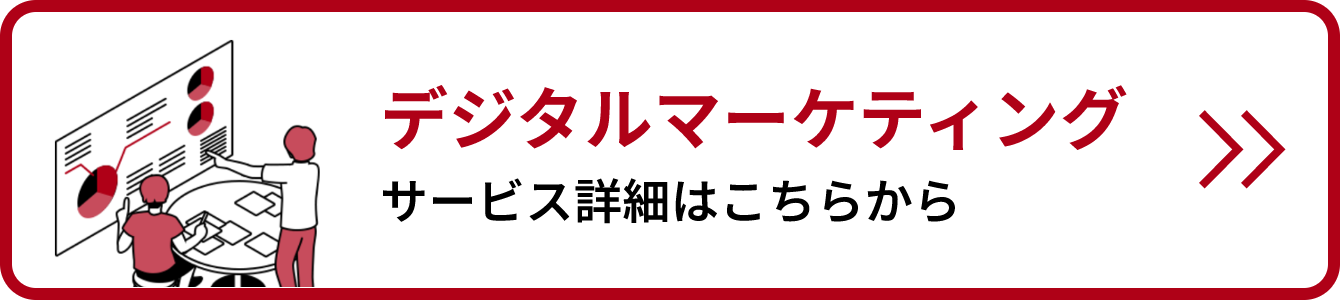
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





