
しかし「ChatGPTやBardなどAIの影響で、SEO手法が変わると聞いたものの実態がよくわからない」「たしかにAI検索も増えたが影響はどの程度?」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、AIの進化に対応したSEO施策と実践的な対策方法を整理してご紹介いたします。「AI時代のSEO対策の基本を知りたい」という方はもちろん、「今後のSEO戦略にどうAIを活用できるか模索している」という方も、ぜひご一読ください。
生成AI時代にSEO対策が変わる理由

それではまず、ChatGPTやBardのような生成AIが、なぜ情報取得手段として広く使われるようになったのか、その背景について以下で説明します。
技術的ブレークスルー
最初に挙げられるのが、生成AIの基盤となるLLMの技術が飛躍的に発展した点です。具体的には、学習データ量の急増と、Transformerモデルなどの高性能なアルゴリズムの登場が挙げられます。これらにより、大量のテキストデータから学習し、文脈を理解して自然な文章を生成する能力が格段に向上。人間が書いた文章と見分けがつかないほど、高品質な回答が可能になりました。
使いやすさと利便性
従来のWEB検索では、ユーザーがキーワードを考えて入力し、膨大な検索結果の中から自分で適切な情報を探し出す必要がありました。一方の生成AIは、人間と会話するように自然言語で質問するだけで、要約された回答を直接得ることができます。これにより、専門知識を持たない一般ユーザーでも簡単にアクセスし、必要な情報を引き出せるようになりました。
さらに、ユーザーの質問の意図を汲み取り、複数の情報源を統合して、個別のニーズに合わせた回答を生成する能力も大きな強みになっています。こうして、特定の分野に関する深い知識や、複雑な内容の要約など、従来の検索では難しかった情報取得が可能になりました。
社会的・経済的ニーズ
日々繰り返される、情報収集や文書作成などの作業を効率化したいという企業や個人のニーズ。これに対し生成AIは、ドキュメントの要約、メールの作成、データ分析など、さまざまな定型作業を自動化することで応え、人々の生産性を向上させる強力なツールとして認識されるようになりました。
また現代社会では、短時間で多くの情報を効率的に得たいというニーズが高まっています。生成AIは、長い記事や複数のWEBページの内容を瞬時に要約できるため、このニーズにマッチ。YouTubeや動画コンテンツの内容を要約する技術も進化しており、情報取得の多様化にも貢献しています。
検索エンジンの変化と共存
Googleをはじめとする大手検索エンジンも、生成AIの技術を積極的に導入。Googleの「AI Overviews」のように、検索結果の上部にAIが生成した要約を表示する機能が導入され、ユーザーの情報取得体験が変化しつつあります。
こうした背景を受け、2025年度に入り6カ月間でAI経由での流入は10倍以上に増加。BtoCのアクセス比率は約0.01〜0.02%と低いもののCVが発生し、またBtoBのアクセス比率は約1%〜2%とBtoCに比べると高くなっています(※)。
※ルビー・グループのクライアント及び関連企業のGoogle Analytics上の数値を参照
ただし、生成AIを情報取得手段として信頼するにはまだまだ問題があります。学習データにない情報をあたかも事実であるかのように生成することがあり(これをハルシネーションと呼びます)。
また、既存のテキストや画像、音声などを学習しているため、その出力が著作権を侵害する可能性があります。さらにはフェイクニュースやディープフェイクなど、悪意のある利用も懸念されており、生成AIによる情報取得は、倫理的な課題も指摘されています。そのため、従来のキーワード検索と生成AIを併用する「ハイブリッド型」の情報収集が、今後の主流になる可能性が指摘されています。
しかしいずれにしても今後は、従来のように検索順位を重用視するだけでなく、「自社のWEBサイトがAIの情報ソースになる」ことが重要になってくることに変わりはないと言えるでしょう。
AIに引用されやすいサイトとは
では、AIに引用されやすいWEBサイトにはどういった特徴があるのでしょうか。
高い信頼性と権威性
AIは、検索エンジンが評価する「E-E-A-T」の概念を重視します。これは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったもので、具体的には、以下の要素が含まれます。
専門家によるコンテンツ
医師や弁護士、特定の分野の専門家など、資格や肩書きを持つ著者が執筆・監修した記事は高く評価されます。
出典・参考文献の明確化
論文、公的機関のデータ、信頼できるニュースソースなど、情報の根拠が明確に示されているサイトは、信頼性が高いと判断されます。
運営者情報の明記
会社概要、所在地、連絡先など、運営者の情報が透明に記載されていることも重要です。
構造化されたコンテンツ
AIは、コンテンツの内容を効率的に理解するために、整理された構造を好みます。
そのため、h1(タイトル)やh2、h3(中見出し)などのhタグを適切に使い、記事の階層構造を論理的に整理しているWEBサイトを引用先として好みます。
また、重要なポイントや手順が箇条書きで分かりやすくまとめられていたり、リスト化されていると、AIが情報を抽出しやすくなります。
さらに、Q&A形式などにより、よくある質問に対する回答が明確に書かれているコンテンツは、AIがユーザーの疑問に答える際に引用しやすい傾向があります。
オリジナリティと独自性
他のサイトの情報をまとめるだけでなく、独自のアンケート調査、実験データ、専門家へのインタビュー、実体験に基づいたノウハウなど、そのサイトでしか得られないオリジナルの情報(一次情報)が豊富であることも重要です。
検索エンジン最適化(SEO)の基本を押さえている
AIは、依然としてGoogleなどの検索エンジンで評価の高いサイトを信頼できる情報源として参照する傾向があります。そのため、以下のSEO対策も間接的にAIに引用されやすくなる要因となります。
ユーザーファーストのコンテンツ
ユーザーの疑問や課題を解決する質の高いコンテンツは、結果的に検索順位が上がりやすくなります。
最新の情報への更新
古い情報ではなく、常に最新のデータや状況を反映しているサイトは、AIが誤った情報を引用するリスクが低いため、好まれます。
これらの特徴を持つWEBサイトは、AIが生成する回答の「根拠」として引用される可能性が高くなります。これは、従来のSEO(検索エンジン最適化)が「人に伝わるサイト」を目指すのと同様に、AI時代では「AIにも伝わるサイト」を目指す「AIO(AI検索最適化)」という考え方に繋がっています。
自社サイトをAIに引用させる具体的施策
自社サイトをAIに引用させるための具体的な施策は、「AIが情報を理解し、信頼できると判断しやすいようにコンテンツを設計する」という考え方が基本となります。
以下に具体的な取り組みを挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。
信頼性と権威性を高める
・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化:AIは、Googleが評価するE-E-A-Tを強く意識します。
・著者情報の明記:記事の著者の専門性(肩書き、資格、経歴)を明確に記載する。
・一次情報の発信:他サイトの引用だけでなく、自社で実施したアンケート調査、実験データ、独自の見解、顧客へのインタビューなど、オリジナルで価値のある情報を発信する。
・運営者情報の透明化:会社概要、所在地、連絡先、事業内容を明確にし、サイトの信頼性を高めます。
・出典の明確化:記事内で引用するデータや事実には、必ず公的機関や信頼できる研究論文などの出典を明記する。
コンテンツの構造化と簡潔化
・明確な見出し(hタグ)の活用:記事の階層構造を論理的に整理し、h1、h2、h3などを適切に使う。これにより、AIが記事の要点を素早く把握できます。
・結論ファーストの記述:記事の冒頭や各セクションの最初に、結論や要点を簡潔にまとめる(「○○とは△△です」のように、定義を1文で端的に記述)。
・箇条書きやリストの活用:メリット、デメリット、手順、特徴などは、箇条書きや番号付きリストで整理する。これにより、AIが情報を抽出しやすくなります。
・Q&AやFAQの充実:ユーザーが抱くであろう疑問に対し、簡潔で明確な回答をセットで提供するFAQページを設ける。これはAIがユーザーの質問に直接回答する際に、最も引用しやすい形式の一つです。
・構造化データ(Schema.org)の活用:HTMLに構造化データを埋め込むことで、記事の著者、公開日、価格、FAQの内容などをAIに正確に伝達する。これにより、AIのコンテンツ理解が深まり、検索結果でリッチリザルトとして表示される可能性も高まります。
AIに伝わる表現を意識する
・平易な言葉で説明する:専門用語は避け、誰にでもわかる平易な言葉で記述する。専門用語を使う場合は、注釈や補足説明を加えます。
・断定的な表現を使う:「〜だと思われます」のような曖昧な表現ではなく、「〜です」「〜があります」のように、断定的な表現を用いることで、AIはより正確な情報だと判断しやすくなります。
・独自の切り口や視点:他のサイトにはないユニークな分析や、体験談、創業ストーリーなど、そのサイトならではの「独自性」を強調する。
これらの施策を講じることで、自社サイトはAIが「信頼できる」「理解しやすい」と判断する情報源となり、AIによる引用の可能性を大きく高めることができます。
成果測定と改善のポイント
AIO(AI検索最適化)の成果測定方法
AIO(AI検索最適化)の成果を測定するには、従来のSEOとは異なる視点が必要です。直接的なアクセス数だけでなく、AIによる引用や情報の利用状況を把握することが重要となります。
具体的には以下の方法を参考にしてみてください。
Google Search Consoleの活用
AI検索での表示回数とクリック数
Googleが「AI Overviews」のような生成AIによる検索結果を表示する機能を提供している場合、その表示回数やクリック率を測定します。これにより、自社サイトがAIの回答にどの程度表示されているかを把握できます。
上位表示キーワードの変化
AIに引用されやすい「〇〇とは」「〜する方法」といった質問形式のキーワードで、検索順位が上がっているかを確認します。
SNSやニュースサイトでの言及の追跡
ブランド名や特定のキーワードの検索
自社のブランド名や、AIが引用しやすいと想定される特定のキーワードを、SNSやニュースサイトで定期的に検索し、AIが生成したコンテンツが拡散されているかを確認します。
逆引き検索ツール
AIが生成した文章の一部をコピーし、検索エンジンで検索することで、引用元のサイトを特定できる場合があります。
直接的なユーザー行動の分析
滞在時間とエンゲージメント率
AIに引用されたことで、サイトに流入したユーザーがどのくらい長く滞在しているか、他のページを閲覧しているかなどを分析します。AIが要約した内容に興味を持ったユーザーは、さらに詳しい情報を求めてサイト内を深く回遊する傾向があります。
コンバージョン率の変化
AI経由の流入が、最終的に製品購入や問い合わせといったコンバージョンに繋がっているかを確認します。
まとめ
生成AI時代のSEO対策は、「AIがユーザーに自信を持って提示できる、信頼性と権威性のあるコンテンツをいかに作り出すか」が鍵となります。ユーザーが何を求めているのかを深く理解し、その答えをAIが理解しやすい形で提供することが、これからのSEO成功の道と言えるでしょう。
ルビー・グループは、単なるECサイトの運営代行に留まらず、ブランドの持つ「信頼性」と「専門性」をデジタル上で最大化することで、生成AI時代のAIOを強力に推進できる役割を担っています。クライアントが持つ情報をAIが「引用したい」と思える形に整理し、発信することで、ブランド価値向上と売上拡大の両方を実現することが可能となります。生成AI時代のSEO対策についてお悩みでしたら、ぜひご相談ください。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

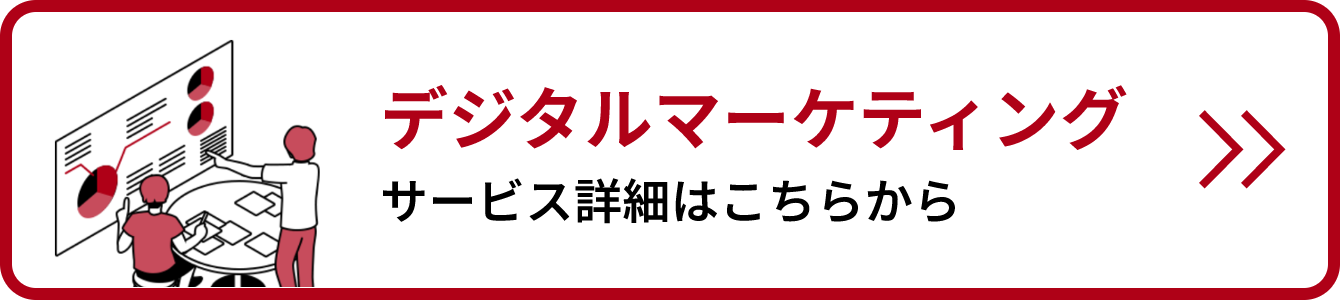
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly