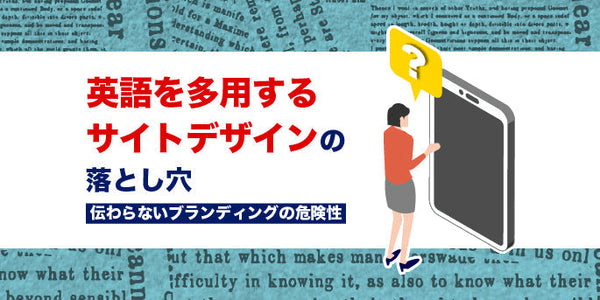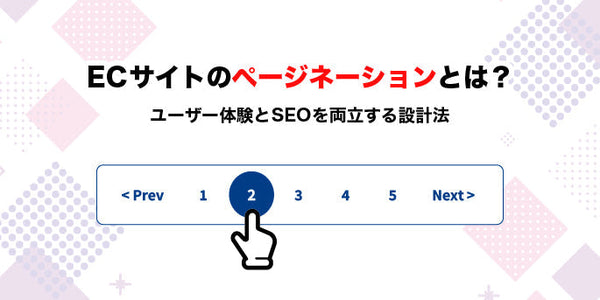そこで本記事では、ECサイトでサーバーが落ちる主な原因と、サーバーダウンを防ぐための基本対策や具体的な施策などについて解説します。
「サーバー落ちの具体的な原因を知りたい」「短期的に解決できる応急処置や、長期的な対策を把握したい」という方はもちろん、「再発防止のためのインフラ設計やクラウド移行などを検討したい」「システムをリプレイスすべきかの判断材料が欲しい」と考えていらっしゃる方も、ぜひご一読ください。
ECサイトでサーバーが落ちる主な原因

ECサイトでサーバーがダウンする主な原因はいくつかあり、大きく分けて「アクセス集中」、「ハードウェア・ソフトウェアのトラブル」、「サイバー攻撃」の3つが挙げられます。それぞれ、詳しく解説していきましょう。
アクセス集中による負荷超過
ECサイト特有の、サーバーダウンの最も一般的な原因の一つです。サーバーが一度に処理できるアクセス数や負荷の限界を超えると、処理が追いつかなくなりダウンします。
とくに、ブラックフライデーや季節のセール、期間限定イベントなど、大規模セールやキャンペーンを展開し、予想を遥かに超えるアクセスが短時間に集中すると、サーバーのリソース(CPU、メモリなど)が限界に達してしまいます。
またテレビなどのメディアや、SNSなどで商品やサイトが取り上げられ、急激に知名度が上がり大量のユーザーが押し寄せた結果、サーバーが耐えきれなくなることがあります。
さらに、人気ブランドのコラボ商品や数量限定アイテムの発売開始直後などは、ファンが一斉にアクセスするため、サーバーに極端な負荷がかかり落ちるケースが散見されます。
ハードウェア・ソフトウェアのトラブル
サーバーを構成する物理的な機器や、運用するシステム側に問題が発生するケースです。サーバー機器のHDD/SSD、CPU、メモリ、冷却ファンなどの部品が、経年劣化や温度変化、物理的な損傷などで故障し、サーバー全体が停止することがあります。
また、ECサイトのプログラムやインストールされているソフトウェアのバグ(不具合)や、サーバーの設定ファイルやリソース割り当ての誤り、OSやアプリケーションのアップデート失敗など、人為的なミスによる設定不備もサーバーが落ちる原因になります。
アクセス集中と関連しますが、CPUやメモリの使用率が常に高い状態が続いたり、データベース処理がボトルネックになることで、レスポンスが遅延し、やがてサービス停止に至るケースもあります。
サイバー攻撃
悪意を持った第三者からの攻撃によって、サーバーがダウンさせられることがあります。複数のコンピューターから同時に大量のアクセスや不正なリクエストを特定のECサイトに集中させる、いわゆるDDoS攻撃 (分散型サービス拒否攻撃)によって、サーバーに過剰な負荷がかかり、サービスが停止させられてしまいます。
また、システムの脆弱性を突いてサーバー内部に不正侵入し、データを破壊・改ざんしたり、故意にサーバーを停止させたりする不正アクセスやマルウェアも深刻なダメージをもたらします。
これらの原因を特定し、事前の対策(例:サーバーのスペック増強、負荷分散、セキュリティ対策の強化、定期的な点検など)を行うことが、ECサイトの安定稼働には不可欠です。
サーバーダウンがEC事業に与える影響
ECサイトのサーバーダウンは、事業にとって非常に深刻で広範囲にわたる影響を与え、単に「サイトが見られなくなる」以上の大きな損失が生じます。ここでは、主に4つの大きな影響について解説します。
直接的な金銭的損失(機会損失)
サーバーダウンの最も分かりやすい影響と言えるでしょう。
売上機会の損失(逸失利益)
サイトが停止している間、顧客は商品の閲覧や購入手続きが一切できません。特にセール中や新商品発売直後など、アクセスが集中する時間帯にダウンした場合、その時間帯に得られたはずの売上が完全に失われます。
プロモーション費用の無駄
広告やSNSキャンペーンなどで多額の費用をかけて集客したにもかかわらず、ユーザーがアクセス時にダウンに遭遇すると、その集客コストが無駄になってしまいます。
復旧・対策コスト
障害発生時の緊急対応や復旧作業にかかる人件費、再発防止のためのシステム増強・改修費用など、予期せぬコストが発生します。
顧客満足度下落とユーザー離れ
ダウンを経験したユーザーは、サイトに対する信頼を失い、競合他社に流出するリスクが高まります。
購入意欲の減退と離脱
欲しい商品があってもサイトにアクセスできない、あるいは読み込みが遅いといった状況に遭遇すると、ユーザーはすぐに購入意欲を失い、別のECサイトで購入しようとします。
ブランドイメージの低下
「このサイトは不安定だ」「重要な時に使えない」というネガティブな印象が定着し、企業のブランドイメージや信頼性が大きく損なわれます。
リピーターの減少
一度離脱したユーザーを呼び戻すには、新規顧客を獲得するよりもはるかにコストと時間がかかってしまいます。
企業の社会的信用の低下
ECサイトは企業の顔であり、安定稼働は最低限の責務と見なされます。
取引先や関係者からの信頼喪失
サーバーダウンが大規模なニュースになった場合や、頻繁に発生する場合、ビジネスパートナーや株主などからの信頼を失うことになります。
個人情報漏洩リスク(サイバー攻撃の場合)
サーバーダウンの原因がDDoS攻撃だけでなく、不正アクセスによるものだった場合、顧客情報や決済情報が流出する危険性があり、企業の社会的信用を決定的に失うことにつながります。
SEOへの悪影響
サーバーダウンは、検索エンジンからの評価にも悪影響を及ぼします。
クロール頻度の低下
Googleなどの検索エンジンがサイトを巡回(クロール)しようとした際にダウンしていると、「質の低いサイト」と判断され、その後のクロール頻度が低下したり、検索順位が下落したりする可能性があります。
インデックス削除のリスク
サーバーダウンが長時間続くと、検索エンジンはサイトが「存在しない」とみなし、検索結果からページが削除(インデックス削除)される最悪の事態もありえます。
サーバーダウンは、短時間の停止であっても売上、信用、将来の集客力にまで影響を及ぼすため、EC事業者にとって最優先で対策すべきリスクの一つです。
サーバーダウンを防ぐための基本対策
ECサイトのサーバーダウンを防ぐためには、主な原因(アクセス集中・機器のトラブル・サイバー攻撃)に対応できるように計画的に進める必要があります。ここでは、EC事業者が取り組むべき基本的な対策を3つの柱に分けてご紹介します。
処理能力の強化と負荷分散(アクセス集中対策)
突発的なアクセス増加に耐えられるインフラ環境を構築することが重要です。
スケーリング
サーバーのリソース(CPU、メモリ)不足を解消するために、サーバーの増強(スケールアップ) や 台数増加(スケールアウト) を行い、処理能力の限界を引き上げます。
ロードバランサーの導入
サーバーの安定稼働を維持するために、複数のサーバーにアクセスを均等に振り分けて負荷分散することで、特定のサーバーに負荷が集中するのを防ぎます。
キャッシュの活用
頻繁にアクセスされる情報(商品画像、トップページなど)を一時的に記憶(キャッシュ)させ、サーバーへのリクエスト回数を軽減。サーバー自体の処理量を大幅に削減し、表示速度も向上させます。
クラウドサービスの利用
アクセス量に応じて、柔軟にサーバーリソースを自動で増減できるクラウド環境を利用することで、必要な時に必要な分だけリソースを確保し、コスト効率を高めることができます。
安定したシステム運用と冗長化(機器・ソフトウェアトラブル対策)
物理的な故障や人的ミスによる停止を防ぐための仕組みを導入します。
サーバーの二重化
重要なシステムやデータベースを複数用意し、現用系がダウンしても待機系に自動で切り替わる仕組みを構築。単一障害点(SPOF)をなくし、機器故障による停止を防ぎます。
定期的なバックアップ
サーバーデータやデータベースを定期的に別媒体に保存し、ダウンやデータ破損が発生した際に速やかに復旧できるようにします。
監視体制の強化
サーバーのCPU使用率、メモリ、I/O(読み書き速度)などを24時間体制で監視し、異常を検知した際にアラートを出す仕組みを導入。サーバーダウンに至る「予兆」を捉え、事前に対処できるようにします。
セキュリティ対策の徹底(サイバー攻撃対策)
悪意ある第三者による攻撃を防ぎ、サーバーを保護します。
DDoS攻撃対策
攻撃による大量のトラフィックを防御・分散するサービス(DDoS緩和サービス)や、WAF(Web Application Firewall)を導入します。
システムの脆弱性対策
OSやアプリケーション、ECシステム(CMSなど)を常に最新の状態に保ち、セキュリティパッチを適用し、攻撃者が侵入に利用できる「穴」を塞ぎます。
不正アクセス対策
強固なパスワードポリシーを設定し、不要なポートの閉鎖やアクセスログの監視を徹底。悪意ある侵入によるシステム停止やデータ改ざんを防ぎます。
将来的な視点で検討すべき施策
ここでは、EC事業を安定的に運用するために検討すべき2つの施策「クラウド環境への移行」と「ECプラットフォームのリプレイス」についてご紹介いたします。
クラウド環境への移行
クラウドへの移行は初期の設計や設定が必要ですが、サーバーダウン対策と事業の成長性を両立させる上で、現在のECサイトの主流な選択肢となっています。主なメリットを、以下でご紹介します。
アクセス集中への柔軟な対応(スケーラビリティ)
ECサイトにとって最大の課題である突発的なアクセス集中に、柔軟に対応できる点が最大のメリットです。
セールやメディア露出などでアクセスが急増した場合、クラウド環境は設定に基づいて自動的にサーバー台数や処理能力(CPU、メモリ)を増やします。
アクセス集中が落ち着けば、リソースを自動で元に戻したり(スケールイン)、停止したりできるため、無駄なコストを削減することができます。必要な時に必要な分だけリソースを使える従量課金制のメリットです。
高い可用性と安定性
クラウドプロバイダーが提供する堅牢なインフラを利用できるため、安定稼働のレベルが格段に向上します。
サーバーやデータベースを複数の異なるデータセンター(アベイラビリティゾーン)に分散配置する冗長化が、比較的容易に実現可能。特定の機器やデータセンターに障害が発生しても、サービスを継続できます。
また、サーバー機器の物理的な故障や老朽化、交換といったハードウェア保守・管理はクラウド事業者が担当するため、自社で対応する手間とコスト、それに伴うダウンリスクから解放されます。
強固なセキュリティと災害対策
自社で高度な対策を施すのが難しいセキュリティと、災害対策の恩恵を受けられるのも大きなメリットです。
主要なクラウドプロバイダーは、DDoS攻撃をはじめとする大規模なサイバー攻撃に対する高度な防御機能を標準で提供していることが多く、ECサイトを保護する上で強力な盾となります。
また、サーバーが遠隔地の安全なデータセンターに分散配置されるため、地震や火災などの自然災害によって自社の拠点が被災しても、ECサイトのサービス停止を防ぐことができます。
運用管理の効率化
システム運用にかかる手間が軽減され、事業成長のための開発に集中できます。
データベースやキャッシュ、ロードバランサーなど、ECサイトに必要な様々な機能が「マネージドサービス」として提供されるため、システムの構築や日々の監視、メンテナンスの手間が大幅に軽減。EC事業のコア業務である商品開発やマーケティングにリソースを集中させることができます。
ECプラットフォームのリプレイス
プラットフォームのリプレイスは大きな投資と手間を伴いますが、サーバーダウン対策だけでなく、EC事業の持続的な成長に必要な基盤を整えることができる、戦略的なメリットの大きい選択肢と言えます。主なメリットは以下の通りです。
最新の技術基盤と高い可用性の獲得
最新のプラットフォームの多くは、最初からクラウド環境での利用を前提に設計されています。これにより、オートスケーリング(自動的なサーバー増強)や負荷分散といった機能が標準で組み込まれており、アクセス集中によるサーバーダウン耐性が飛躍的に向上します。
また古いプラットフォームに多い、すべての機能が一つの大きなシステムにまとまった構造(モノリシック)から、機能ごとにシステムを分けるマイクロサービスなどのモダンな構造へ移行できます。これにより、特定の機能(例:決済、在庫管理)に負荷が集中しても、システム全体がダウンするのを防げます。
さらに、古いシステムでは対応が難しかったセキュリティ脆弱性が解消され、最新のセキュリティ基準に準拠したシステムを導入できるため、サイバー攻撃によるダウンリスクを大幅に軽減できます。
パフォーマンスの根本的な改善
新しいプラットフォームは、最新のWeb技術を使ってページの読み込み速度を最適化する設計が取り入れられていることが多く、レンダリング(表示)速度の最適化により、サーバーダウンの直接的な原因となる「処理の遅延」を解消するだけでなく、ユーザーにストレスのないEC体験を提供できます。表示速度の向上は、コンバージョン率(購入率)の向上にも直結する重要なポイントです。
運用・保守コストの適正化
古いプラットフォームを使い続けると、ベンダーのサポートが終了し、不具合やセキュリティリスクが発生しても対応してもらえなくなるリスクがあります。リプレイスにより、長期的なサポートを受けられるようになり、システムの安定性が確保されます。
また、管理画面の使いやすさが向上したり、外部サービスとの連携(API連携)が容易になったりすることで、日々のシステム運用にかかる人件費や手間を削減できます。
まとめ
サーバーダウン対策は、単なるITの技術的な問題ではなく、EC事業の収益、顧客基盤、そしてブランドを守るための、経営上の最重要課題です。
しかも上記でご紹介したような対策は一度行えば終わりではありません。ECサイトが成長すればするほど、サーバーダウンのリスクは高まります。また、サーバーダウンを引き起こす外部要因は常に進化しています。そして、一度でも対策を怠ると、いざという時の対応が非効率的になりコストが増大します。事業規模やイベント計画に合わせて継続的にサーバーダウン対策を見直し、強化していくことが非常に重要なのです。
サーバーダウン対策は「終わりのないマラソン」であり、EC事業の成長に合わせて計画的かつ継続的に見直し、投資し続けることが不可欠と言えるでしょう。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

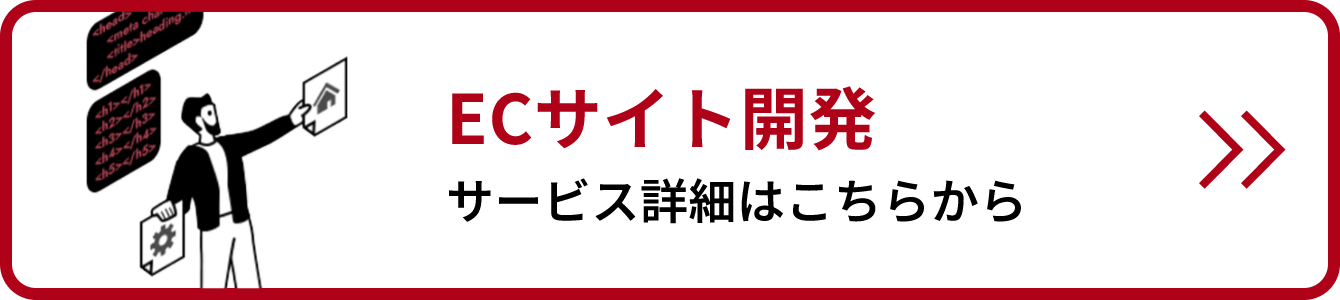
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly