
本記事では、中国インバウンド市場の最新動向と訪日客の行動傾向や、中国人観光客に響く情報発信・SNS活用術、オンラインとオフラインをつなぐ集客・販促戦略などについてご紹介しています。
「最新の中国インバウンド市場動向・旅行トレンドについて知りたい」「中国人観光客に効果的な集客手段(SNSや口コミサイトなど)を調べている」という方はもちろん、「SNSでの認知→来店→購買→UGC拡散までのファネル設計を検討中」「どのようにして越境ECとインバウンドの相乗効果をもたらすかを考えている」という方も、ぜひご一読ください。
中国インバウンド市場の最新動向と訪日客の行動傾向

2014年から中国の急速な経済成長に伴う中国人の可処分所得の増加を背景に、中国からの訪日旅行客数は毎年最高を記録し続け、2019年には約959万人に至りました。
その後、コロナ禍の影響で大きく減少したものの、2023年から訪日客数が回復、2024年には698万人に。さらに、2025年1月には前年同月比+135.6%増の約98万人に達し、コロナ禍以前の訪日客数の水準へと回復が継続しています。
中国人観光客が再び増えている背景には、以下のような要因があります。
団体旅行の解禁
2023年8月、中国政府は日本を含む78の国と地域への団体旅行を解禁。これにより、3年半ぶりに中国からの団体旅行が日本でも可能になりました。
ビザの緩和
2024年11月には、中国外務省が2025年12月31日までの措置として、ビジネスや観光目的の30日以内の短期滞在であれば、ビザなしでの渡航が可能になることを発表しました。さらに、日中間航空便の再開などもあり、今後も中国からの訪日客の増加が期待されています。
それでは中国人訪日客の行動傾向には、以前と比べてどのような変化が見られるのか。具体的に見ていきましょう。
「安価な商品の大量購入」から「品質やブランド重視」へ
最近の中国人観光客の買い物内容のうち、購入者単価の高い品目トップ5は以下の通りです(※)。
1.宝石・貴金属
2.時計・フィルムカメラ
3.靴・かばん・革製品
4.衣類
5.化粧品・香水
中国人観光客の購入単価は高額化しており、以前の安価な商品を大量に購入するスタイルから、品質やブランドを重視する傾向へと変化しています。
高額な宝飾品や高級ブランド品、高品質な日本ブランド化粧品などの需要は、今後も期待できるでしょう。
※参照元:日本政府観光局(JNTO)|日本の観光統計データ 項目別の購入者単価(https://statistics.jnto.go.jp/graph/#graph--average--spending--per--capita--by--category)
消費の中身は、モノからコトへ
近年の中国観光客は、以下のような体験型イベントを重視する方も増えています。
◆舞台・音楽鑑賞
◆自然体験ツアーの参加
◆映画・アニメの聖地巡礼
◆ポップカルチャーの体感 など
上記のような体験型コンテンツは写真や動画映えするため、SNSで共有するのに最適です。SNSを活用するZ世代を中心に、こうした体験型イベントニーズは今後も拡大していくでしょう。
訪問地は、都市から地方へ
訪日回数の増加とともに、東京・大阪といった主要都市の訪問率は少しずつ低下し、地方エリアの訪問率が上昇傾向にあります。
とくに北海道は、広大な自然や温泉、グルメなどが楽しめるため、中国の富裕層を中心に人気があります。ニセコやルスツなどのスキーリゾートは、冬のウィンタースポーツを楽しむために多くの中国人観光客が訪れています。
また、温泉やグルメ、歴史的な観光スポットなどが豊富な九州は、幅広い層の中国人観光客に人気があります。特に、別府や由布院などの温泉地は、リラックスや癒しを求める観光客に人気があります。その他にも、沖縄は美しい海やビーチ、亜熱帯の自然が人気です。
情報源は圧倒的にSNSとインフルエンサー
中国人観光客は、日本旅行の情報源としてSNSを非常に重視しています。中国で人気のSNSは以下の通り。
『抖音(Douyin)』
ショート動画を通じて旅行先の魅力を効果的に伝え、クーポンや限定オファーを提供することで、訪日旅行のきっかけを作りやすいとされています。
『小紅書(RED)』
中国版Instagramとも呼ばれ、体験談や口コミが数多く投稿され、トレンドに敏感な若い女性ユーザーに人気があります。
『WeChat』
中国で広く利用されているSNSで、情報収集だけでなく、決済やコミュニケーションにも活用されています。
また「KOL」「KOC」といったインフルエンサーの影響力は大きく、旅行情報だけでなく、商品やサービスの情報源としても活用されています。
中国人観光客に響く情報発信・SNS活用術
まず、中国インバウンド対策に必要な1つ目の視点が、「SNSの活用」です。インターネット利用者の9割以上がSNSを利用している中国では、SNSはブランディング、プロモーションをおこなう上では欠かすことのできないツールとなっています。
ここでは、「小紅書(RED)」をはじめとしたSNSの活用術や、インフルエンサーマーケティングの事例などについてご紹介します。
「小紅書(RED)」は、「世界中の良いモノが見つかる」をコンセプトに中国で開発されたソーシャルプラットフォームです。
30歳未満の女性を中心に3億人が利用していると言われ、主にライフスタイルや美容、コスメ、ファッション、旅行、グルメなどの情報を共有する場として知られています。
「小紅書(RED)」はコミュニティ性が高く、ユーザー同士の交流が活発なのが大きな特徴。投稿に対するエンゲージメント(いいね・コメント・シェア)が非常に高く、口コミ効果が期待できます。
さらに、商品のタグ付け機能が充実していて、特定の商品のレビューや情報を見つけやすくなっているため、ユーザーが商品に関する情報を効率的に収集しやすく、広告以上に高い集客効果が期待できます。
中国人観光客はSNSでの口コミやリアル体験をもとに情報収集をし、行先や購入品の検討などを行います。「小紅書(RED)」のようなリアルな口コミやレビューに定評があるプラットフォームを活用すれば、効果的な中国人インバウンド対策を実施できます。
なお、最新版の小紅書(RED)アプリは翻訳機能を搭載しており、日本語で内容を閲覧することも可能なので、ぜひ参考にしてみてください。
中国の若い女性から圧倒的な人気を獲得している「小紅書(RED)」ですが、ユーザーが小紅書(RED)上で自社の商品やサービスを検索をしても、口コミがなければ発見してもらえません。そこで重要となってくるのが、信頼性の高い「KOL」「KOC」を活用した施策です。
「KOL」と「KOC」は、いわゆる中国版のインフルエンサー的な存在で、「KOL」(Key Opinion Leader)は、特定の分野に精通した一定の専門性と信頼性をもつユーザーで、「KOC」(Key Opinion Consumer)は、あくまで消費者としての立場で発信し、一定の影響力を持っているユーザーを指します。
広島の最高級ブランド榊山牛(さかきやまぎゅう)で有名な「肉匠ふるさと」(東京 銀座)は、フォロワー数は少ないものの高いエンゲージメントが期待できる「KOC」を積極的に活用したプロモーションを実施。その結果、利用者の8割が中国人となり、春節などの中国の長期休みは満席、顧客単価も140%向上と高い成果につながっています。
受け入れ体制の整備で信頼と満足度をアップ
中国インバウンド対策に必要な2つ目の視点が、「受け入れ環境の整備」です。ここでは、国内店舗内での中国語表示の重要性や、QRコード決済導入の必要性などについて解説いたします。
中国語対応は、デジタルサイネージなどを活用する
中国人インバウンドを受け入れる日本の店舗や施設がどんどん増えていますが、簡単には越えられないのが言語・コミュニケーションの壁です。言語の壁を取り払うことが出来れば、中国人観光客とのコミュニケーションが円滑になり、リピーターの増加や口コミによる新規顧客の獲得が期待できます。
具体的な方法としては、店頭のポスターなどの掲示物やPOPなどに、商品名やサービス名などを中国語表記するといった施策が行われていますが、さらに、デジタルサイネージを活用するという方法もあります。
デジタルサイネージは、主に液晶ディスプレイやLEDパネルなどの表示機器を使い、ネットワークを通じてコンテンツを配信するシステムで、動画や音声も簡単に配信できるため、ポスターや掲示板よりも動的にわかりやすく訴求できます。もちろん多言語対応も可能なので、店舗や施設を訪れた中国人観光客にも効果的に中国語で商品やサービスの訴求を行うことが可能になります。
特別感の演出や体験型イベントの設置
言語対応以外にも積極的に取り組むべきなのが、特別感の演出やイベントの設置です。
たとえば大手ホテルチェーンでは、春節時期に合わせた館内装飾や限定プランの提供により特別感を演出。さらに、チェックイン時にWeChatミニプログラムを活用したスムーズな案内を行うことで、満足度の向上に成功しています。
また、とあるショッピングモールでは、「小紅書(RED)」で話題となりそうなフォトスポットや体験型イベントを設置し、自然なUGC(ユーザー投稿コンテンツ)を生み出す仕組みを構築。中国人観光客自身が情報発信することで、更なる集客に繋がっています。
QRコード決済対応は必須
さらに重要になるのが、決済環境の整備。特にキャッシュレス決済への対応は必須と言ってよいでしょう。
訪日外国人観光客の中でも、特に中国・韓国・東南アジアからの旅行者は、QRコード型のモバイル決済を日常的に利用しています。中国ではAlipay(アリペイ)とWeChat Pay(ウィーチャットペイ)の2大サービスが圧倒的なシェアを持ち、現地では現金よりもこちらが主流という状況です。
QRコード決済の特徴は、利用者のスマートフォンにアプリがインストールされていれば、言語や通貨に関係なく即時決済が可能な点にあります。日本の店舗側は、専用端末やプリントされたQRコードを提示するだけで対応できることが多く、導入コストや運用の手間も軽減可能。
訪日客にとっては慣れた方法で支払える安心感があり、店舗側にとってもリスクが少ないスムーズな決済ができます。
オンラインとオフラインをつなぐ集客・販促戦略
そして、中国インバウンド対策に必要な3つ目の視点が、「旅中の集客・旅後のリピート促進」になります。ここでは、来店導線の確立方法や、リピーター獲得のための施策についてご紹介します。
来店導線の確立は「Google Map」で
中国人が事前リサーチをする際にもっとも利用する手段は「SNS」や「口コミサイト」ですが、日本に到着後に利用する情報収集ツールが、実は「Google Map」です。全81の言語に対応し、世界中のユーザーが自分の言語でお店の情報を見ることができます。
また、レビューの内容が訪問を決める重要な情報源になるのは、インバウンド客も同じ。Google Mapは、クチコミの自動翻訳に対応しており、ユーザーの設定言語に合わせて翻訳してくれます。
なお、Google Mapのビジネスプロフィールでは、店舗の営業時間、連絡先、写真、メニューなど、様々な情報を多言語で登録可能。多言語に対応しており、店舗名や説明文などを、日本語だけでなく、中国語(簡体字・繁体字)でも登録・表示できます。これにより、中国人観光客に店舗情報を正確に伝えることができます。
さらにGoogle検索結果においても、ビジネスプロフィールの情報は上位に表示されやすいため、ホームページなどを持たない店舗にとっても、検索ユーザーへのプロモーションとなる重要な存在です。
旅行前は中国国内のSNSでプロモーションをし、日本到着後はGoogle Mapで来店の導線を確立しましょう。
囲い込みやリピート促進は「WeChat」で
WeChat(微信)は、、中国版LINEとも言われるメッセンジャー機能を中心としたマルチサービスアプリで、インバウンド客の多い日本企業のマーケティングにおいて有効なツールです。
たとえば、来店時に利用できるクーポンページを公式アカウント内に設置することで「旅中」での来店を促進。さらに、実店舗にWeChatの公式アカウントやミニプログラムのQRコードを掲載し、来店・購入していただいた顧客に対して公式アカウントへのフォローを誘導します。
また、公式アカウントをフォローしたユーザーに対して、記事配信、DM、WeChatグループでの日々のコミュニケーションを行うことによって、顧客のファン化やリピーターの獲得、友人への紹介、越境ECでの購入などに繋げていくことができます。
まとめ
訪日中国人は個人旅行客、団体旅行客問わず、日本に来る前にインターネットで情報収集をし、旅行のプランを考え、購入するものもリストアップして日本に旅行に来ます。そのことも踏まえ、「旅前」「旅中」「旅後」の3つのステージで、訪日中国人に対する有効なインバウンド対策をしましょう。
「旅前」SNSでプロモーション
中国人観光客は「旅行前のSNS・口コミ情報」を重視しています。中国の主要なSNSプラットフォームである「小紅書(RED)」「WeChat」などを活用し、情報を発信しましょう。ポイントは「口コミ情報」を発信をしてもらう仕掛け作りです。
「旅中」中国語表示・中国QRコード決済の導入
デジタルサイネージなどで中国語表示をすることで、中国人顧客の理解を深め、購買意欲を高めることができます。また、中国ではQRコード決済が一般的です。AlipayやWeChat Payなどの中国の主要な決済サービスを導入することは非常に重要です。せっかく購入しようと思ってもQR決済ができないという理由で購入の機会を逃さないようにしましょう。
「旅後」WeChatでリピート促進
WeChat公式アカウントをフォローしてもらったユーザーに対して、人気の商品情報やキャンペーン情報などを定期的に発信し、リピート促進や越境ECの売上につなげましょう。
日本国内の観光地・小売事業者にとって、中国インバウンド対応は売上を伸ばす大きなチャンスですので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を書いた人

ルビー・グループ コーポレートサイトチーム
各分野の現場で活躍しているプロが集まって結成されたチームです。
開発、マーケティング、ささげ、物流など、ECサイトに関するお役立ち情報を随時更新していきます!

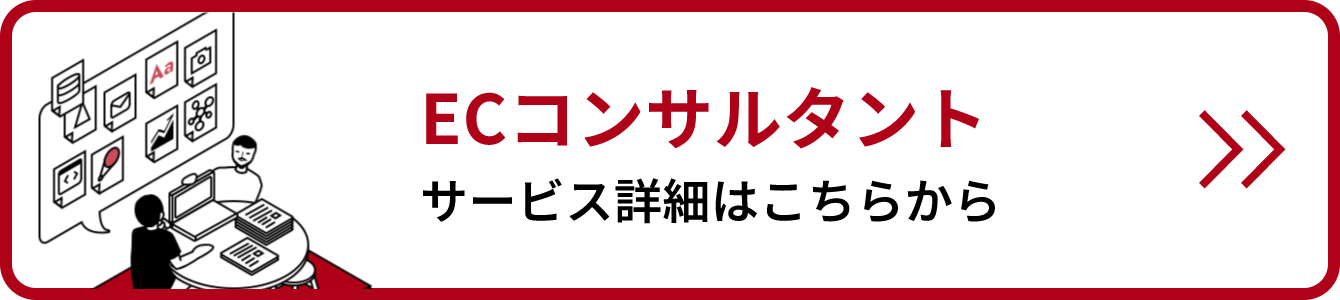
 Post
Post
 Share
Share
 LINE
LINE
 Hatena
Hatena
 Pocket
Pocket
 feedly
feedly





